孫への贈与が特別受益の対象になるケースや相続における注意点とは?
孫への贈与は原則として特別受益ではない
孫や子の配偶者のように、法定相続人ではない人への生前贈与は珍しいことではありませんが、その贈与が過当すぎて、相続財産がほとんど残らないとすれば、他の相続人は不満に思うでしょう。
法定相続人が生前贈与を受けると特別受益に該当する可能性があるのに対し、法定相続人ではない人への生前贈与は特別受益に該当しません。
民法における特別受益の規定は、あくまでも共同相続人を対象としているからです。
また、法定相続人以外への贈与まで含めて遺産分割するのは、対象が広くなりすぎて相続分の確定に支障をきたします。
孫への贈与は特別受益にならないからこそ、トラブルの元になりやすいともいえるでしょう。
孫への贈与が特別受益になる3つのケース
孫への贈与が特別受益になる可能性はゼロではないため注意が必要です。
例えば、以下の3つのケースでは、孫への贈与が特別受益に該当する可能性が高いです。
孫が代襲相続人になる場合
被相続人の子は相続順位が第1順位で法定相続人となります。
しかし、その子がすでに死亡している場合、子の代わりに孫が相続人になります。
これを「代襲相続」といい、法定相続人と同じとみなされます。
つまり、孫が代襲相続人になる場合、公平性を維持するために、贈与が特別受益になる可能性があるのです。
ただし、子が亡くなる前に孫へ贈与があっても、相続権を持たない状態ですから、特別受益には該当しません。
子が亡くなった後に孫へ贈与された場合に限って、特別受益として扱うことになるでしょう。
孫を養子にした場合
孫と養子縁組をすると、法律上の関係性が「親子」になり、孫も法定相続人とみなされます。
法定相続人への贈与は特別受益となるため、孫が養子になった以降の贈与は特別受益になる可能性があります。
事実上は子への贈与にあたる場合
孫への贈与が特別受益に該当しないとしても、贈与の目的が孫の親、つまり相続人に対する贈与を意味する事情も当然にあり得ることです。
そのため、「孫への贈与は全て特別受益に該当しない」と一律で判断するのではなく、被相続人の意思も確認した上で、個々の事案で事情を考慮し、実質的には誰に贈与されているのかを判断するべきです。
その結果、形式的には孫への贈与でも、実質的には相続人への間接的な贈与だと判断できるようなら、遺産分割協議または調停・審判でも、特別受益と主張することは妨げられないでしょう。
相続人以外でも特別受益とされた例
被相続人から相続人(娘)の夫に土地の贈与があった例で、家庭裁判所が相続人の特別受益とみなして遺産分割するべきとした審判を示したケースがあります。
この件は、相続人夫婦が農家であり、相続人の夫に贈与されたのも農地でした。
つまり、生前から農業を手伝っている相続人に対し、農地を与えて謝礼する意図があったものと考えられるのですが、相続人の夫に贈与したのは、夫をたてるべきだと判断したからと推測できます。
このように、実際は相続人以外への贈与でも、相続人と親族関係にある者であれば、実質的には相続人に対する贈与と判断されることもあります。
家庭裁判所は、相続人が形式的な贈与の対象者ではなくても、その贈与によって相続人が利益を受け、相続人同士で不公平が生じているときは、背景にある贈与の経緯や性質などを考慮し、特別受益として遺産分割をするべきという趣旨の判断を示しています。
孫への贈与で注意すること
孫への贈与を考えている人は、以下の2点に注意してください。
法定相続人の遺留分を侵害しない
遺産分割によって遺留分が問題になるケースでは、生前贈与が遺留分の算定に含まれることもあります。
相続開始前1年間の贈与が対象ですが、被相続人と孫の双方が遺留分を侵害すると知りながら行った贈与は、相続開始前の10年間が対象となります。
財産の大半を孫に生前贈与してしまうと、遺留分が侵害されたとして、法定相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性があるでしょう。
もし、相続人である子が被相続人である父親より先に亡くなっている場合、孫が相続権を持ちます。
贈与税や相続税の対象になることがある
生前贈与を孫に行う場合、最低限必要とされる入学金や学費、生活費は贈与税の対象外となります。教育資金の一括贈与制度を利用すれば、1人につき1,500万円まで非課税で贈与が可能です。
しかし、孫の前年の合計所得が1,000万円以下であること、23歳以上になると非課税の範囲が限られること、在学中でなければ30歳で制度の対象外になることなどの要件があるため注意が必要です。
また、毎年の贈与(暦年贈与)の場合も、年間110万円以内なら非課税ですが、非課税枠を超えて贈与をしてしまうと、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産とみなされ、課税対象になります。
まとめ
子ではなく孫に資金援助を行うケースは非常に多いですが、「特別受益になるか否か」で孫と法定相続人との間で揉める例は少なくありません。
生前贈与であっても、相続が始まった時に相続人が遺留分を主張する可能性があるため、バランスを考慮して援助することが大切です。
孫への贈与や相続税対策でお困りの方は、専門家である弁護士にご相談ください。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
相続の関連コンテンツ
- 遺産分割調停が不成立になると「遺産分割審判」になる?
- 事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)がもしもの時に相続はどうなる?
- 障害児の親が面倒を見る家族・兄弟に全財産を相続することは可能?
- 自分以外の兄弟が親の生前にまとまった額を受け取っていた場合の相続は?
- 実家を生前贈与する場合の問題点と名義変更の方法について
- 孫への贈与が特別受益の対象になるケースや相続における注意点とは?
- 生涯独身で一人暮らしの高齢者の相続はどうなる?親族が面倒を見た場合は?
- 銀行の「遺言信託」を利用するメリットとデメリット
- 特定の子どもを相続人から除外(相続排除)することは可能?
- 子どもに喜ばれる生前贈与のやり方や節税のための注意点とは?
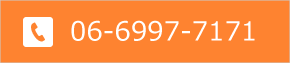


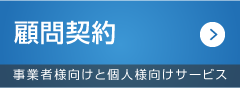
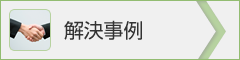
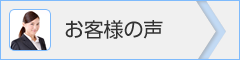
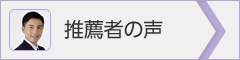
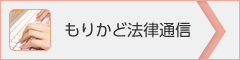
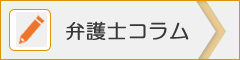

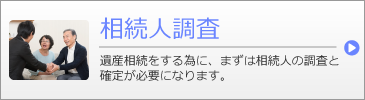
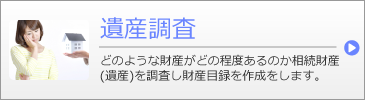
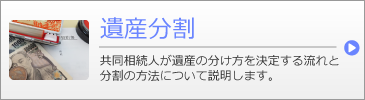
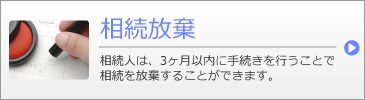
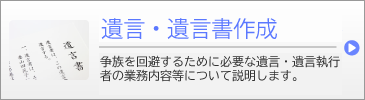
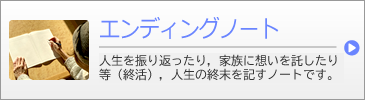
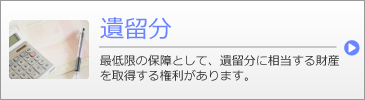
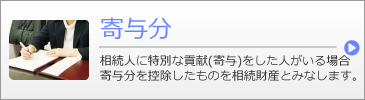
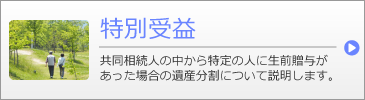
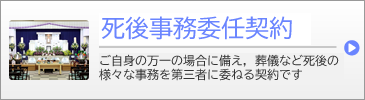
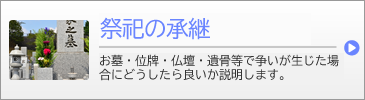
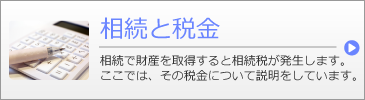
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)
![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](/common/img/btn_sp_tel.png)

