実家を生前贈与する場合の問題点と名義変更の方法について
実家の生前贈与の名義変更の流れ
実家を長男など子どもの名義にすることで、生前贈与することになります。
必要な手続きは、二つあります。
1.贈与契約書を作る
贈与契約は、口約束であっても契約は成立します。
しかし、口約束の場合は前言撤回されてしまう可能性があり、後々に言った言わないの堂々巡りの議論になってしまうことも考えられます。
そういったトラブルを防ぐためにも、事前に贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与契約書を作っておくことで、所有権移転登記をする際にも活用できます。
贈与契約書は、「登記事項証明書」を確認して間違いのないように土地の登記内容について書き記しましょう。
「登記事項証明書」は、法務局で取得することができます。
2.登記の手続き
生前贈与の登記手続きに要する書類は、おおむね以下の通りです。
・贈与契約書
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書と実印
・以前の登記済み権利証または登記識別情報通知書
・運転免許証などの本人確認書類
また、現住所が現状の登記簿の記載と異なる場合は、上記に加えて住民票の写しが必要となります。
登記の手続きには必要な書類が多くあり、さらに労力及び時間がかかります。
そのため大半の方は、司法書士に依頼します。
司法書士に依頼することで、必要な書類なども不備なく準備してもらえます。
以上が、被相続人と相続人同士で行う場合に必要な手続きです。
ただし被相続人が遠方に住んでいたり、入院しているといったケースも考えられます。
そういった場合に必要なこととして、代理人を立てておくことです。
現在の所有者の判断能力などに特段問題がないとしても、将来相続人同士で言い争いが起こらないように、しっかりとした代理人を立てておきましょう。
可能であれば弁護士や司法書士に依頼するなどして、適切な契約書を作成しておくことが望ましいです。
特に所有者が認知症である場合は、慎重に対応していく必要があります。
ケースに合わせて、後見人や保佐人、補助人を立てて進めることが想定されます。
後見は、認知症や知的・精神障害などにより判断能力が欠けている状態について、家庭裁判所の審判を経て、本人をサポートする成年後見人を選任する制度です。
ただし、被後見人の居住用不動産を処分するためには、必ず家庭裁判所の事前の許可が必要となるため、後見制度での生存贈与は基本的に難しい状況です。
一方で判断能力がある程度残っているケースでは、家庭裁判所の審判を受け、保佐人、補助人という制度を使って進めていきます。
本人の自己決定権を保護しつつ、一定の範囲内で保佐人、補助人に代理権や同意見が与えられますが、実家の贈与という重大な問題であるため、弁護士などに相談しながら対応することをおすすめします。
名義変更に要する税金や費用
財産分与による名義変更を除き、不動産の名義変更を行うには主に4つの税金がかかります。
1.不動産所得税
名義変更後の所有者に対する税金が、不動産所得税です。
税額は、不動産の固定資産税評価額に所定の税率をかけて計算します。
2.名義変更登記・登録免許税
通常名義変更は司法書士に依頼するため、その報酬を考えなければなりません。
また、登記の手続きの際に課される国税もあります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に2%の税率をかけて求めます。
相続の場合の税率は0.4%であり、各種の免税措置があります。
3.印紙税
贈与契約書の作成時、契約書に貼らなければならない印紙があるため印紙税がかかります。
印紙税は契約書に記載がなければ200円、記載がある場合はその金額となります。
4.贈与税
贈与税は、受ける人と贈与する人の関係で2種類の税率があります。
直系尊属から20歳以上の子どもや孫への贈与では、特例税率があり、それ以外では一般税率が課されます。
実家を生前贈与する場合は、いくつか注意点があります。次の文章では、具体的な問題点についてみていきましょう。
実家の生前贈与で相続分が減る可能性もある
生前贈与によって長男に実家を渡すと、遺産分割の際に、長男以外の相続人から特別受益にあたると主張されてしまうかもしれません。
ちなみに特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特別の利益のことを表します。
相続は一般的に、法定相続人が法定相続分に応じて遺産分割をするのが原則です。
しかし、一部の相続人が特別に優遇を受けているケースでは、各相続人間の公平をはかるために優遇されていた相続人の相続分を減らすことを認めるのが、特別受益の考え方になります 。
特別受益として認められた場合でも、生前贈与された自宅は相続財産に含まれませんが、相続分の計算においては自宅を含めた合計額が使われます(特別受益の持ち戻しといいます)。
長男の相続分は、自宅の価額を控除することになり、その結果マイナスになってしまうと、長男は相続で何も受け取ることができなくなります。
ただし、自宅は相続財産に含まれていないので、相続分がマイナスになったとしても、長男が自宅を差し出すようなことにはなりません。
また、長男への生前贈与に相続の趣旨がなく、自宅を完全に外した遺産分割を望むのであれば、持ち戻しを免除するように取り計らうことも可能です。
その際は、遺言書を書くなら遺言書に、遺言書を書かないとしても書面として残る形にしておきます。
なお、持ち戻しの免除があったところで、長男以外の相続人が持つ遺留分までは侵害できません。
長男以外は遺留分侵害額請求ができる
自宅以外の主だった財産がないときは、長男に自宅を生前贈与することで、長男以外の相続人が何も受け取れなくなり、遺留分を侵害していることになるため、長男に対して遺留分侵害額請求をする可能性があります。
そうすると、遺留分によって自宅は長男と他の相続人による共有状態となってしまいますが、長男が共有状態を望まないときは、遺留分に相当する金額を他の相続人に支払うことで解消できます。
遺留分侵害額請求は相続開始前の1年間に行われた贈与の他、遺留分を侵害すると知って行われた贈与なら、相続開始の1年以上前であっても可能であることから、仮に長男が相続放棄をして相続人から外れても状況は好転しません。
したがって、長男が遺留分の侵害に対処するだけの資金を用意できる前提で、自宅を生前贈与しないとトラブルの元です。
大きな生前贈与には相続時精算課税制度
生前贈与には贈与税がかかり、贈与税は基礎控除が年間110万円しかなく税率も高いため、金額(価額)の大きい財産を生前贈与してしまうと、相続税よりも税金面で不利を受けます。
これを理由に生前贈与を控える人が多かったのですが、相続税の特例として相続時精算課税制度があるので検討してみましょう。
相続時精算課税制度では、60歳以上の親や祖父母が、20歳以上の子や孫に生前贈与をする場合、2500万円までの贈与で贈与税を非課税とする代わりに、相続財産へ生前贈与分も含めて相続税を計算する制度です。つまり、生前に行われるのであくまでも贈与ですが、実質的には相続を生前に行うような制度になっており、生前贈与がしやすいと言えます。
まとめ
以上、ここまで説明した内容は実家の生前贈与を行ううえでの基本的な流れとなります。
ご実家の贈与にあたり、兄弟や相続人間で争いがおきないように事前の準備をしておく必要があり、税金の問題もあります。
そのため様々な事情に合わせて、適切な選択肢を検討していく必要があります。
可能であれば弁護士など専門家のアドバイスを受けて、ふさわしい解決策を見つけていくことが望ましいでしょう。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
相続の関連コンテンツ
- 遺産分割調停が不成立になると「遺産分割審判」になる?
- 事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)がもしもの時に相続はどうなる?
- 障害児の親が面倒を見る家族・兄弟に全財産を相続することは可能?
- 自分以外の兄弟が親の生前にまとまった額を受け取っていた場合の相続は?
- 実家を生前贈与する場合の問題点と名義変更の方法について
- 孫への贈与が特別受益の対象になるケースや相続における注意点とは?
- 生涯独身で一人暮らしの高齢者の相続はどうなる?親族が面倒を見た場合は?
- 銀行の「遺言信託」を利用するメリットとデメリット
- 特定の子どもを相続人から除外(相続排除)することは可能?
- 子どもに喜ばれる生前贈与のやり方や節税のための注意点とは?
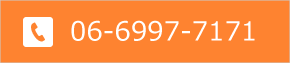


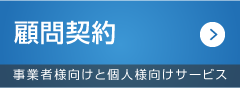
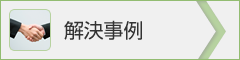
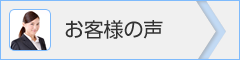
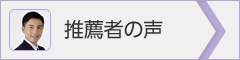
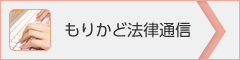
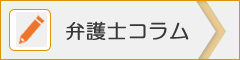

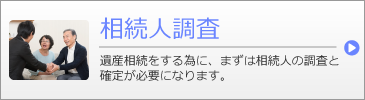
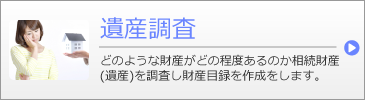
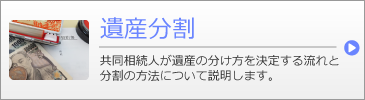
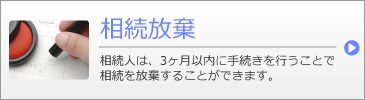
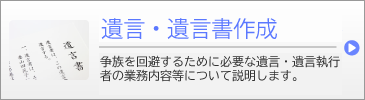
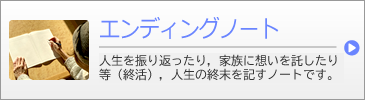
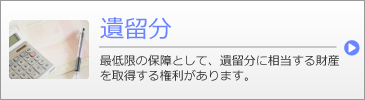
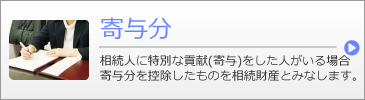
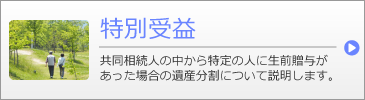
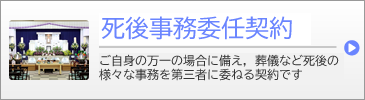
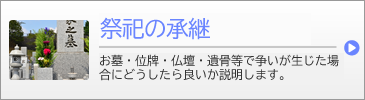
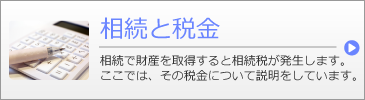
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)
![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](/common/img/btn_sp_tel.png)

