事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)がもしもの時に相続はどうなる?
事実婚の定義やメリット・デメリットは?
そもそも、事実婚とはどのようなことなのでしょうか。
定義やメリット・デメリットについて、解説します。
事実婚の定義

婚姻届を提出しないため、夫婦の戸籍が作成されることはありません。
夫婦はそれぞれの実家の戸籍のままとなり、お互いに結婚前の姓を名乗ることができます。
同じ戸籍ではないものの、夫婦としての権利・義務(※)は発生しますし、結婚式を挙げ、周りに夫・妻として紹介することに問題はありません。
※貞操義務(パートナー意外と性的な関係を持たない)、同居(特別な事情を除く)、生活面での協力(生活費・養育費の分担)など
事実婚のメリット・デメリット
事実婚は、婚姻届を出す必要がなく、戸籍を変更する必要がありません。
そのため、実家の戸籍に籍を置き続けることが可能です。
苗字を変える必要もなく、夫婦別姓で生活することができます。
これらの点は、事実婚のメリットと捉えられています。
自動車の免許証や銀行などで、氏名変更の手続きを行う必要もありません。
また、パートナーの親族と姻族関係にならないため、パートナーの親族と関わりたくない場合にも有効です。
職業的な理由などで独身であることが求められる場合、一旦は事実婚という形にし、徐々にふたりの関係を周囲に浸透させていことができる点も、メリットのひとつと考えられます。
事実婚のデメリットは、法律上の夫婦関係が認められない点です。
パートナーの法定相続人になれないため、遺産相続ができません。
ふたりの間に子どもが誕生した場合にもデメリットがあります。
子どもは母親の戸籍に入るので、法的な父子関係は発生せず、父親の姓を名乗ることもできません。
父子関係を結ぶには「認知」の手続きが必要ですが、親権は母親になります。
親権を父親に変更することは可能ですが、親権を認められるのは母親・父親のいずれかになり、ふたりで親権者になることはできないのです。
そのほか、所得税の配偶者控除制度や、相続税の配偶者税額軽減が利用できない点もデメリットです。
事実婚の相続について
事実婚をした夫婦は内縁関係となります。
内縁のパートナーは法律上の配偶者に該当しないので、どれだけ親密な関係で一緒に財産を築き上げたとしても、形式的には他人ということで相続の権利が認められていません。
内縁のパートナーに相続財産を譲り渡したいと考えている場合には、「婚姻届を提出する」「特別縁故者の制度を利用する」「遺言書を残す」といったことが必要になります。
婚姻届を提出する
婚姻届の提出、つまり一般的な結婚(入籍)の形式をとることにより相続権が認められます。
言葉にすれば簡単ですが、内縁関係にある状態のふたりにとっては何かしらの事情によってこれができないことも多いはずです。
「相続権がなければ財産分与をすればいい」と思うかもしれませんが、財産分与請求権も法律上の夫婦にあたえられた権利であるため(民法第786条)、内縁のパートナーが行使できる権利ではありません。
特別縁故者の制度を利用する
内縁関係があった場合、家庭裁判所に特別縁故者の申し立てをして認められることで、被相続人の財産を受け取ることができます(民法958条の3)。
もっとも、被相続人に子供や兄弟などの法律上の相続人が1人でもいる場合には、特別縁故者としては認められないため注意が必要です。
生前贈与をする
生前贈与は、贈与する人と贈与される人の関係を問いません。
事実婚のパートナーにも、問題なく贈与することができます。
ただし、年間の贈与額が110万円を超えると、受贈者は贈与税を申告しなくてはならず、注意が必要です。
また、生前贈与しきれず財産が残ってしまった場合、パートナーは受け取る権利がありません。
生前に贈与以外で財産を残したい場合、「遺言書を残す」「生命保険の受取人をパートナーにする」という方法もあります。
遺言書を残す
遺言書における財産分与は、相続人以外の他人であっても有効性が認められれば財産を譲ることができます。
ただし「内縁の妻に全て財産を譲る」との旨の遺言書を残しても、被相続人に法律上の相続人がいると一定の遺留分が認められているため、全財産を譲ることは難しい可能性があります。
事前にそれを考慮した内容にしておくと、後々の揉め事も少なく済むはずです。
まとめ
事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)に、もしものことがあった場合、事前に対策をしておかないと財産を残すことはできません。
なぜなら、事実婚は法的な夫婦と認められておらず、法定相続人になれないからです。
事前対策としては、生前贈与や遺言書の作成が効果的です。
事実婚にはメリット・デメリットがありますが、相続に関してはデメリットが大きいため、元気なうちにパートナーと話し合っておきましょう。
相続や遺言書について、自分自身で手続きを行うのは手間がかかりますし、難しい部分もあります。
確実に希望の相続ができるように、法律のプロである弁護士にご相談ください。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
相続の関連コンテンツ
- 遺産分割調停が不成立になると「遺産分割審判」になる?
- 事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)がもしもの時に相続はどうなる?
- 障害児の親が面倒を見る家族・兄弟に全財産を相続することは可能?
- 自分以外の兄弟が親の生前にまとまった額を受け取っていた場合の相続は?
- 実家を生前贈与する場合の問題点と名義変更の方法について
- 孫への贈与が特別受益の対象になるケースや相続における注意点とは?
- 生涯独身で一人暮らしの高齢者の相続はどうなる?親族が面倒を見た場合は?
- 銀行の「遺言信託」を利用するメリットとデメリット
- 特定の子どもを相続人から除外(相続排除)することは可能?
- 子どもに喜ばれる生前贈与のやり方や節税のための注意点とは?
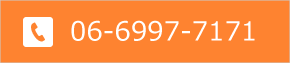


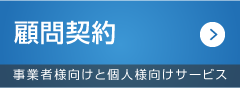
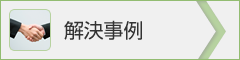
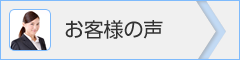
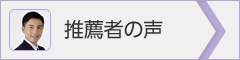
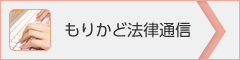
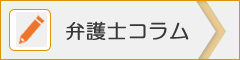
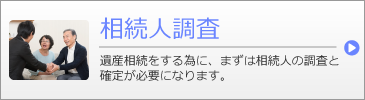
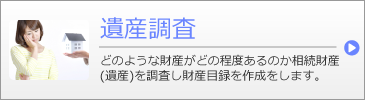
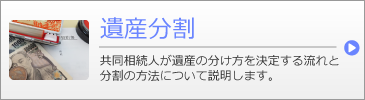
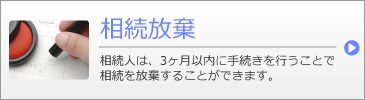
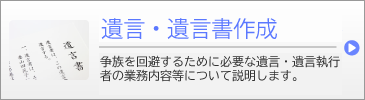
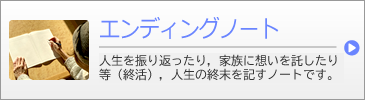
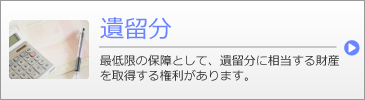
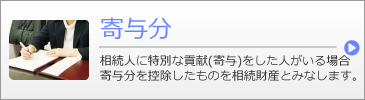
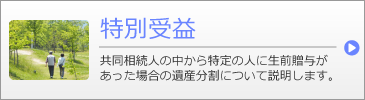
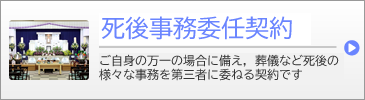
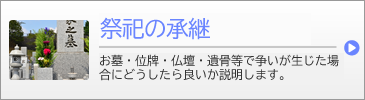
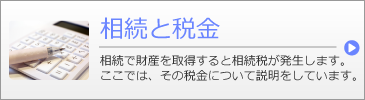
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)
![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](/common/img/btn_sp_tel.png)

