自分以外の兄弟が親の生前にまとまった額を受け取っていた場合の相続は?
父親が亡くなる前に、自分以外の兄弟姉妹が、結婚費用や開業資金を出してもらっていた場合「相続が兄弟姉妹で平等に分けられるのは納得いかない」と感じる人も多いのではないでしょうか。
今回は、姉が結婚費用200万円、兄が開業資金900万円を受け取っていて、自分はそういった援助を受けていないという想定で考えてみたいと思います。
遺贈や生前贈与は特別受益の可能性
法定相続分は、兄弟姉妹(被相続人の子)であれば均等ですが、共同相続人の中に、遺贈や特定の生前贈与を受けた人がいるときは、特別受益として相続分の計算が変わってきます。
民法第903条による規定では、「遺贈」と「婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与」を特別受益としています。特別受益がある人の相続分は、相続財産に特別受益の価額を加えた総額を、法定相続分に分割して特別受益を控除した金額です。
つまり、特別受益がある人は相続分が少なくなるので、特別受益の認定が大事になってくるわけです。
特別受益の要件
法文上での特別受益は、「遺贈」と「婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与」ですが、遺贈や生前贈与が行われた背景・事情や財産全体に対する影響も考慮されます。というのも、姉が受け取った結婚費用200万円は、生計の資本として受け取ったのか、結婚に伴う一時的な費用(挙式費用など)として受け取ったのかで、財産的性質が変わってしまうからです。
仮に遺産が3000万円ある状態で、1割に満たない200万円が姉の挙式費用に使われたとしても、挙式費用を親が出してあげるのは珍しいことではないですし、特別受益にならないほうが多いと思われます。
しかしながら、兄の開業資金900万円については、遺産に対する割合も大きく生計の資本として受け取ったことが明確ですので、特別受益と認定されるでしょう。その場合、相続財産は3000万円に特別受益900万円を加えた3900万円とみなされます。
兄、姉、あなたの3人で3900万円を分けると1人1300万円ですが、兄は特別受益900万円を控除され400万円が相続分です。
特別受益は認定されにくい
寄与分においては、寄与分を定める処分の調停・審判が独立して存在しますが、特別受益においてそのような具体的手続は完備されていません。したがって、遺産分割調停・審判のような他の手続きで特別受益の存在を主張していくことになります。
ところが、特別受益は記憶が曖昧、何も証拠がないなど当時の記憶頼りも多く、こうした事情で、特別受益は1割程度しか認められていないことが、司法統計によって示されています。特別受益だとする根拠を具体的に証拠で示さない限り、特別受益の主張は難しいということです。
被相続人は持ち戻しの免除が可能
特別受益があると、相続財産に特別受益の価額を加えて(持ち戻しといいます)、相続分を計算することになりますが、被相続人から特別受益に該当しないとの意思を表明することも可能です。
その場合、持ち戻しは免除され、特別受益として扱われないことになりますが、遺留分を侵害している部分までは、効力を与えることはできません。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
相続の関連コンテンツ
- 遺産分割調停が不成立になると「遺産分割審判」になる?
- 事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)がもしもの時に相続はどうなる?
- 障害児の親が面倒を見る家族・兄弟に全財産を相続することは可能?
- 自分以外の兄弟が親の生前にまとまった額を受け取っていた場合の相続は?
- 実家を生前贈与する場合の問題点と名義変更の方法について
- 孫への贈与が特別受益の対象になるケースや相続における注意点とは?
- 生涯独身で一人暮らしの高齢者の相続はどうなる?親族が面倒を見た場合は?
- 銀行の「遺言信託」を利用するメリットとデメリット
- 特定の子どもを相続人から除外(相続排除)することは可能?
- 子どもに喜ばれる生前贈与のやり方や節税のための注意点とは?
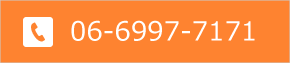


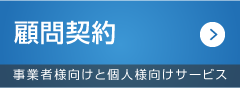
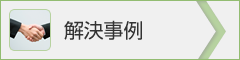
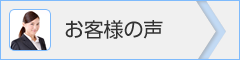
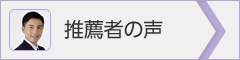
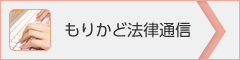
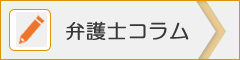
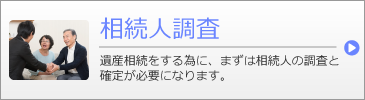
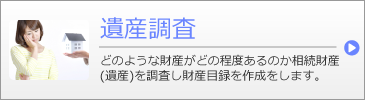
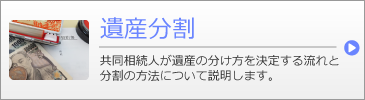
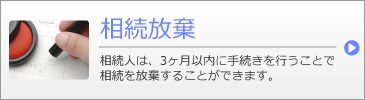
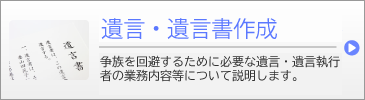
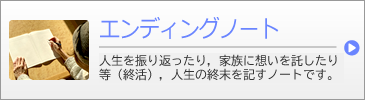
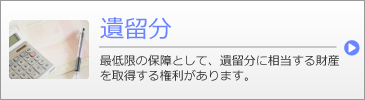
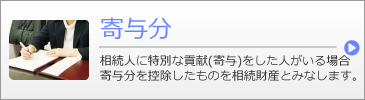
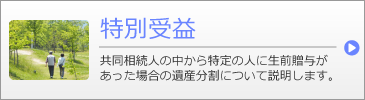
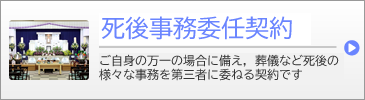
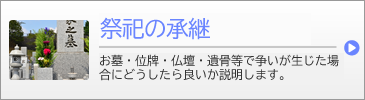
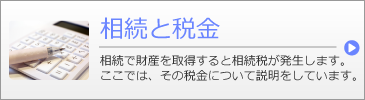
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)
![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](/common/img/btn_sp_tel.png)

