生涯独身で一人暮らしの高齢者の相続はどうなる?親族が面倒を見た場合は?
おひとりさまが亡くなった時の法定相続人は誰になる?
生涯独身のおひとりさまが亡くなった場合の法定相続人について、考えてみましょう。
亡くなった人の父親・母親が生きていれば、法定相続人になります。
片親だけ生きている場合は、片親が法定相続人です。
また、両親が離婚をしている場合も親子関係は続いているので、父親・母親とも法定相続人として認められます。
父親・母親が亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人です。
両親・祖父母の全員が亡くなっている場合は、独身の人の兄弟姉妹が法定相続人になりますが、兄弟姉妹も亡くなっている場合はその子ども(甥姪)が法定相続人になります。
その他、生涯独身の人が養子縁組をしているケースであれば、養子が最優先で法定相続人となり、両親・祖父母、兄弟姉妹、甥姪が法定相続人になることはありません。
生涯独身で、両親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪・本人の養子がいない場合は、法定相続人に該当する人がいない(相続人がいない)ことになります。
どのような人がこのような状況になりやすいかというと「一人っ子で両親・祖父母が亡くなっている」「両親・祖父母・兄弟姉妹が全員亡くなっていて、兄弟姉妹にも子どもが一人もいない」といった場合です。
いくら親族だからといってお世話をしていても、法定相続人に該当しなければ、基本的に相続は受け取れないということになります。
相続者がいないケースでの相続手続
上記のように相続人がいない場合、相続手続きはどうなるのでしょうか。
相続人の存在が不確かな折(相続人が不在の際も)、相続財産は法人扱いされ、利害関係者ないし検察官の請求によって家庭裁判所(家裁)が選定した相続財産管理人(一般的には弁護士)がその管理を行います。
相続財産管理人が目録を作成して相続財産を管理した上で、相続人がいるかいないかを調査し、被相続人の債権者に弁済を行うなどして、残った財産は国庫に属する流れになります。
つまり、相続財産管理人によって財産が清算され、国のものになるということです。
法定相続人でない親族が、面倒を見ていたからといって、勝手に財産を処分したり自分のものにしたりすることは許されません。
しかし、面倒を見ていた親族は、亡くなった人の特別縁故者(特別な関係にあった人物)に該当します。
詳しくは次項で紹介しますが、亡くなった人の療養看護を行っていた人も特別縁故者になります。
よって、この場合でも、独り身のお年寄りのお世話をしている近親者は利害関係者として、相続財産管理人の選任を家裁に要求すべき運びになります。
しかし、その際は相続財産管理人の報酬などの費用として、数十万円~100万円という大金を前もって納める義務が生じます。そして、プラスになる相続財産が存在しなければ、そのお金は返ってきません。
ゆえに相続財産管理人制度の利用者は少なく、近しい人が必要な範囲で最低限の後処理を行って、預金などの相続財産などをそのままにしているというパターンが大半です。
特別縁故者に対する財産分与
特別縁故者になるのは、次の①~③のいずれかに該当する人です。
①被相続人と家計を共にしていた人間
②被相続人の看護や世話などを行っていた人間
③特別縁故者(被相続者と特殊な関わりがあった人間)
ただし、特別縁故者の立場で財産分与してもらうのであれば、その事を証明できなければなりません。
例えば、身の回りの世話をしてきたというのであれば、その事を見て取れる資料を用意しておく必要があります。
そしてこの手続きは多大な期間を要し、実際に分与を享受できるのは、相続財産管理人選定の申し入れから1年以上後になることが考えられます。
財産分与の請求期間にも制限があるので注意が必要です。
加えて、家裁は相続財産管理人の考えを参考にしながら特別縁故の内容・程度を審理するため、確実に分与を受けられるという保証はありません。
債権者への弁済を相続財産管理人が完了した際に残った財産があれば、家裁に相続財産の一部または全ての分与を求める事が可能です。
包括遺贈を検討してみる
包括遺贈は、財産内容を指定することなく遺贈ができます。
例えば「遺産すべてを、面倒を見てくれた、親族のAさんに遺贈します」といった指定が可能です。
特別縁故者や相続財産管理人の制度は手間がかかりますし、出費もかさむので多くの方が便利ではないと感じるはずです。この制度を使う代わりに、できれば前もって遺言書を作ってもらい、遺贈を行ってもらうとスムーズです。
遺言書にて相続財産全ての包括遺贈(全部を相続させる、という趣旨の遺贈)をしてもらっておくと、包括遺贈人は相続者と同等の義務と権利を有する事になるので、「相続人がいない」という扱いにはならず、周りの人々に苦労をかけなくて済みますし、億劫な処理を行わなくてよくもなります。
ただし、包括遺贈は負債(マイナスの遺産)も遺贈することになってしまいますので、相続責務の引継ぎについては注意しましょう。
一方、一部遺言(財産の一部分だけを遺贈するという趣旨の遺言)に関しては、やはり相続人不存在に関する処理が必須になるので、おすすめできません。
また、相続財産全ての包括遺贈の場合でも、名義変えなどの処理の際には遺言執行者が欠かせませんので、遺言を通して遺言執行者を明確にしておくべきです(明確になっていない際には、家裁に遺言執行者の選定を申し立てます)。
説明してきた通り、相続人がいないと、存外ややこしい手続きに追われる事になります。悔いの無いよう早めに、面倒を見てあげている人と一緒に弁護士に相談すると良いですね。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
相続の関連コンテンツ
- 遺産分割調停が不成立になると「遺産分割審判」になる?
- 事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)がもしもの時に相続はどうなる?
- 障害児の親が面倒を見る家族・兄弟に全財産を相続することは可能?
- 自分以外の兄弟が親の生前にまとまった額を受け取っていた場合の相続は?
- 実家を生前贈与する場合の問題点と名義変更の方法について
- 孫への贈与が特別受益の対象になるケースや相続における注意点とは?
- 生涯独身で一人暮らしの高齢者の相続はどうなる?親族が面倒を見た場合は?
- 銀行の「遺言信託」を利用するメリットとデメリット
- 特定の子どもを相続人から除外(相続排除)することは可能?
- 子どもに喜ばれる生前贈与のやり方や節税のための注意点とは?
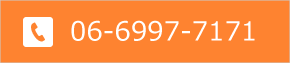


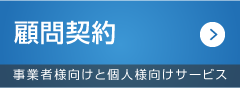
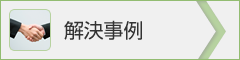
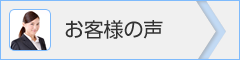
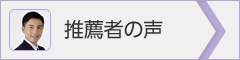
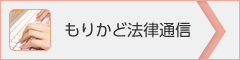
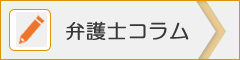

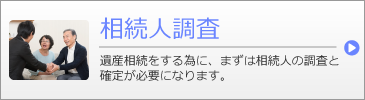
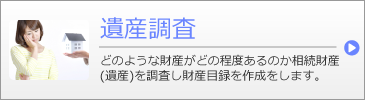
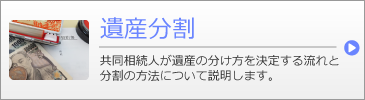
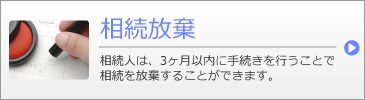
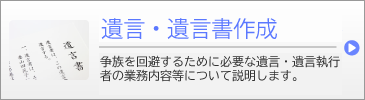
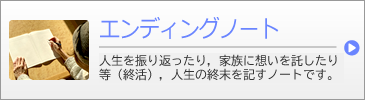
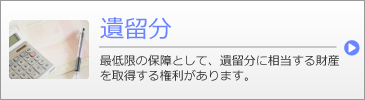
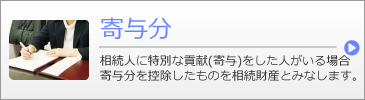
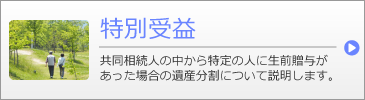
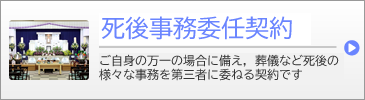
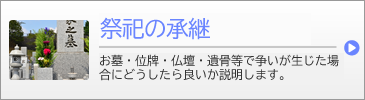
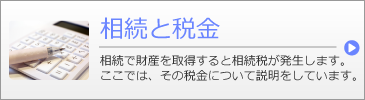
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)
![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](/common/img/btn_sp_tel.png)

