祭祀に関する権利の承継 – 弁護士によるサポート
祭祀の承継とは、家族や先祖の供養に関連する権利や義務を次世代に引き継ぐことを指します。
これは、墓地や仏壇、位牌の管理、さらには法要の実施などが含まれます。
これらの権利は、相続財産とは異なる性質を持ち、民法に基づき、被相続人の意思や家庭の慣習を尊重して承継されることが基本です。
しかし、祭祀を巡る争いは、相続人間で意見が対立する場合や、被相続人の意向が不明確な場合に発生しやすいです。
当事務所では、祭祀に関する権利の承継について法的なアドバイスを提供し、円滑な解決を目指します。
当法律事務所のサポート内容
祭祀承継者の決定支援
被相続人が遺言で明示していない場合、祭祀を承継する者を法的観点から決定します。
慣習や相続人間の話し合いを基に、公平な解決を図ります。
遺言書作成における祭祀承継の明記
祭祀に関する権利を特定の相続人に引き継ぐ場合、遺言書に明記することでトラブルを防ぎます。
当法律事務所では、法的に有効な遺言書作成をサポートします。
墓地や仏壇の管理に関する相談
墓地の使用権や仏壇の所有権など、祭祀財産の扱いについて適切なアドバイスを提供します。
必要に応じて、関連する法的手続きも支援します。
祭祀費用の分担に関する調整
祭祀にかかる費用を相続人間で公平に負担するための話し合いや調整をサポートします。
家庭裁判所での調停・審判の代理
祭祀承継者が決まらない場合や、相続人間で争いが発生した場合には、家庭裁判所での調停や審判を通じて解決を目指します。
感情的な対立の緩和
祭祀に関する問題は感情的な対立に発展しやすいため、冷静かつ公平な調整を行い、家族間の対立を最小限に抑えます。
祭祀継承に関連する法律相談
祭祀に関する承継が相続財産とは異なる特性を持つことを踏まえ、法的な観点から適切なアドバイスを行います。
祭祀に関する権利の承継の重要性
祭祀に関する権利の承継は、家族や先祖への尊敬を表し、次世代にその意義を伝える重要な役割を担っています。
一方で、家庭内での話し合いが不十分だったり,元々不仲だったりすると、トラブルが発生しやすい分野でもあります。
当法律事務所では、祭祀に関する問題をスムーズに解決し、依頼者が安心して祭祀を引き継げるよう全面的にサポートいたします。
祭祀に関する疑問やお困りの点がございましたら、ぜひ当法律事務所までご相談ください。
経験豊富な弁護士が、依頼者の意向に寄り添いながら、公平で円満な解決を目指します。
1.はじめに

相続(争族)争いや,遺産分割協議に関連して,どの相続人が,お墓を守っていくのか,位牌や仏壇を管理していくのか,遺骨を預かるのか等が争いになることがあります。これは,祭祀に関する権利をどの相続人が承継するかの問題であり,現行民法は897条で規定しています。
2.現行民法の趣旨
戦前の旧民法においては,祭祀財産は「家督相続ノ特権に属ス」(旧民法第987条)と規定されており,家督相続人が独占的に承継していました。しかし,戦後は家督相続の制度が廃止されました。
もっとも,家督相続という従来の慣行や一般の国民感情への配慮・祭祀財産は分割になじまないこと等より,一般の遺産相続とは別に,本規定が設けられました。
3.祭祀財産の内容
系譜:祖先の系統を示すもの(家系図・過去帳など)
祭具:祭祀の用に供するもの(位牌・仏壇・仏具・神棚など)
墳墓:墓石・墓碑・墓地の所有権・墓地使用権
4.祭祀財産の承継者
現行民法897条は,祭祀財産は,「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が承継すると規定したうえで,その祭祀主宰者の決定方法について,以下のように規定しています。
第1次的:被相続人の指定により決める。
第2次的:被相続人の指定がないときは,その地方の慣習により決める。
第3次的:被相続人の指定がなく,慣習も不明であるときは,家庭裁判所の審判による指定によって決める。
ここで,祭祀主宰者には特別の資格は不要です。また,相続人か否か,親族関係の有無,氏の異同等も問わないとされています。さらに,系譜・祭具の承継者と墳墓の承継者とが別人になることも許容されるとされています。
なお,被相続人による指定の方法には,特別の限定はないため,生前行為・遺言も可であり,また,書面または口頭,明示または黙示のいずれも可とされています。
家庭裁判所が審判により祭祀主宰者を指定する場合の基準としては,承継者と被相続人との身分関係のほか,過去の生活関係及び生活感情の緊密度,承継者の祭祀主宰意思や能力,利害関係人の意見等諸般の事情から総合的に判断して決定されます。もっとも,祭祀はその性質上,死者の生前時に対する感謝の念から執り行われるべきものですから,遠方にいる血縁者よりも,実際の生活関係・生活感情に鑑みて上記感謝の念をより強く抱く者が選定されるべきと考えます。
5.祭祀財産承継者の地位
祭祀財産の承継においては,相続における承認や放棄のような規定がないため,放棄や辞退はできません。
もっとも,当然に,祭祀の義務を負うわけではありません。また,祭祀主宰者であることを理由に,遺産分割協議において,特別の相続分や祭祀料をもらうことは認められません(もっとも,相続人の合意があれば別)。
ただ,祭祀の主宰には費用がかかることは間違いありませんので,被相続人が祭祀主宰者を指定する際には,その費用に見合った生前贈与・遺贈等をすることが望ましいでしょう。
6.遺体・遺骨について
遺体・遺骨は,判例上,他の有体物・動産と同様に扱うことは適切ではなく,仮に所有権を認めるとしても,性質上,埋葬管理と祭祀供養の目的にとどまるとされています。
所有権が誰に帰属するかは争いがあり,相続人に帰属するという考え・喪主に帰属するという考えがありますが,最高裁は,遺骨について慣習に従って祭祀主宰者に属する,と判断していますので,喪主に帰属することになると考えられます。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](../common/img/header_tel.png)
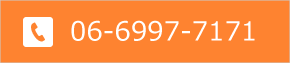


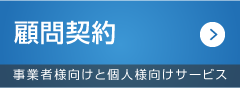
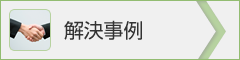
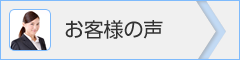
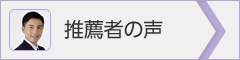
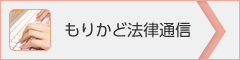
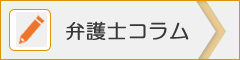
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)
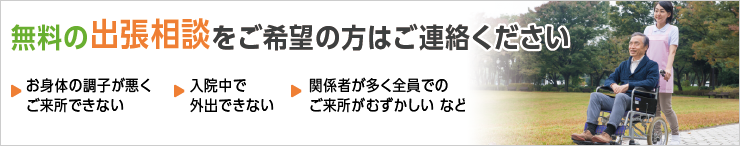
![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](../common/img/btn_sp_tel.png)


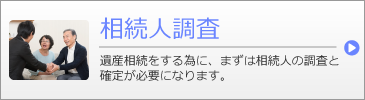
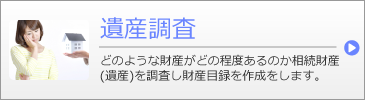
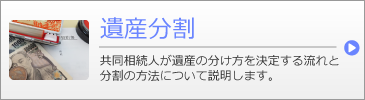
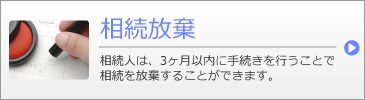
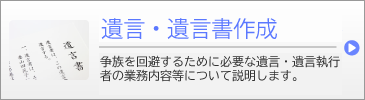
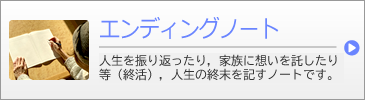
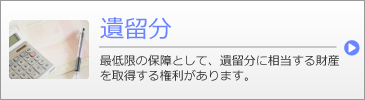
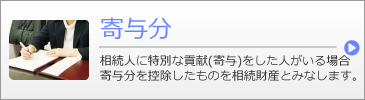
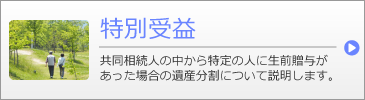
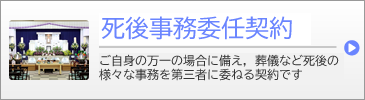
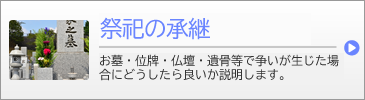
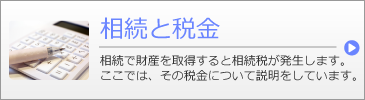
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](../common/img/bnr_contact01.png)

