遺産分割に関するトラブルとその解決策 – 弁護士によるサポート
遺産分割は、相続人間の話し合いに基づいて行われますが、相続財産の分配を巡る意見の違いや、感情的な対立が原因でトラブルに発展することがよくあります。
特に、遺言書がない場合や、その内容に不満がある場合は、家族間での争いが長期化しやすく、法的な対応が必要となることも少なくありません。
当法律事務所では、こうした遺産分割に関するトラブルに対し、依頼者の権利を守りながら、公平かつ円満な解決を目指します。
当法律事務所のサポート内容
遺産分割協議のサポート
相続人全員が合意できる内容での遺産分割協議を実現します。
特に、遺産の配分を巡る意見の相違がある場合でも、法的な視点から調整し、合意に導きます。
法定相続分の確認と調整
各相続人が受け取るべき法定相続分を確認し、不平等感が生じないよう調整します。
遺言書がない場合の遺産分割
遺言書が存在しない場合でも、法律に基づいた遺産分割の手続きを進めるためのアドバイスを行います。
遺産評価や不動産の分割サポート
不動産や金融資産の評価を行い、公正な分割ができるようサポートします。
特に、不動産の分割は複雑な場合が多いため、専門的なアドバイスを提供します。
感情的な対立の調整
遺産分割は家族間の感情的な対立を引き起こすことがあります。
当法律事務所では、感情的な側面も考慮しながら、冷静かつ公正な解決を図ります。
遺産分割における事前準備の重要性
遺産分割に関するトラブルは、事前に適切な準備を行うことで未然に防ぐことが可能です。
遺言書の作成や、財産の評価・管理を事前に進めておくことで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな相続手続きが進められます。
当法律事務所では、遺産分割に関する事前準備のサポートも行っております。
1.遺産分割の流れ

共同相続人が裁判外で話し合いを行い、その中で遺産の分け方などを決定していく、これが遺産分割の基本です。もしこの話し合いで折り合いがつかない場合、調停・審判という形で次のステップへと進むことになります。
裁判所を介する手続として,家庭裁判所では、まず遺産分割調停が行われ(「調停前置主義」といいます。)調停で解決できなかった場合,さらに遺産分割審判へと移行します。
そのほか,遺産分割審判に対する不服申立て手段として抗告審,その抗告審に対する不服申立て手段として特別抗告や許可抗告なども手続上保障されていますが,現実として抗告審以後の手続が利用されることはほとんどありません。
2.裁判外の遺産分割協議における相続分・分割方法の決め方
一般的な遺産分割協議においては,共同相続人間で自由に話し合いを行い,分割の方法や各相続人の相続分を決定します。
当事者同士が納得すればよく,一人がすべての遺産を取得するなどの遺産分割協議を行うことも当然可能です。
遺産分割の方法は,主として「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3種に分けられます(これに,複数の相続人が共有状態を維持したまま相続する「共有分割」を加え,4種とする場合もあります。)。遺産分割の方法については,後に詳しく説明します。
3.遺産分割調停における相続分・分割方法の決め方
裁判所を介するものの、共同相続人が話し合いを行うことで解決を図るのが遺産分割調停です。
話し合いにより解決を図る点は裁判外の遺産分割協議と同じですが、調停では,裁判所が法的な見解を踏まえて各相続人の言い分を整理し、妥当な解決に向けた働きかけを行います。それにより当事者にとってある程度納得がいく形の遺産分割の合意がなされることになります。
通常,裁判外の遺産分割協議においては,相続人同士が互いにいがみ合って,法的な主張としては到底通り得ないことも好き勝手に言い合うことも多々あるので,裁判所が上記のような交通整理を行い,場合によって当事者に説得を試みることで,よりスムーズに合意が促進されることになります。
一方で,遺産分割調停は,裁判手続とはいえあくまで話し合いの場ですから、当事者同士が納得すれば,各相続人の相続割合,分割方法なども自由に合意することが可能です。
言ってみれば、遺産分割調停は,話し合いと裁判の双方の利点を兼ね備えた手続といえるでしょう。
4.遺産分割審判における相続分・分割方法の決め方

遺産分割調停が成立しなかった場合(「調停不成立」や「不調」といいます。)、原則として遺産分割審判へ移行します。
調停が不調に終わるということは、相続人同士の主張に対立が見られるということですが,その争いに対し裁判所が法律に則って判断を下すのが遺産分割審判です。
一般の訴訟に対応するもので,訴訟の場合,当事者間に和解が成立しなかったとき,最終的に裁判所が「判決」を下すことによって事件を終結させますが,遺産分割審判においても,最終的に家庭裁判所が「審判」を下すことによって事件を終結させます。
したがって,当事者の意見が紛糾する場合であっても,必ず一定の決着を見るに至ります。つまり、遺産について,どういう分割方法で,誰が何を、あるいはどの割合で相続するかが法律(民法や家事事件手続法など)を元に決定されることになります。
もっとも、審判とはいえ,当事者間で決着済みの事項まですべて審理していては非合理ですから,実務的には,先の調停等において部分的に当事者間の合意が形成されている場合には,その部分に関しては審判の対象から外す運用となっています。
例えば、土地の遺産分割において共同相続人2名が双方2分の1の割合で取得する点は合意しているが、一方が土地そのものの分割(現物分割)を希望し、もう一方が売却した上での金銭の分割(換価分割)を希望していた場合、その分割方法について審判がなされることになります。
5.遺産分割の方法
(1)現物分割
相続の対象となる財産をその性質・形状を保ったまま分割する方法が、現物分割です。
複数の相続人が共有する状態を解消し、それぞれの相続人が単独で所有権を取得するために用いられます。
複数の不動産を現物分割する場合においては,不動産の評価の仕方(固定資産評価額,路線価,時価など。あるいは借地権の評価をどうするか等)によっては,当事者間に不公平が生じるため,個々の不動産をどのように評価するのかが争点になりえます。
(2)代償分割
現物分割することが困難な遺産の場合などは、共同相続人の一部にそれを相続させ、その者に残りの相続人に代償金を支払わせることで解決する方法があります。これが代償分割と呼ばれるものです。
例えば、財産を残し亡くなった人物が住宅を持っており、そこに住んでいた共同相続人の1人がその住宅を単独で取得し、その代わりに、他の相続人の取得分に応じた代償金を支払う場合などが、この代償分割にあたります。
*遺産分割審判においては
遺産分割審判において代償分割の方法が採用されるためには「特別の事情」が必要であるとされています。(家事事件手続法195条)
裁判例(大阪高等裁判所昭和54年3月8日決定)を参考にしますと,ここにいう「特別の事由」があるときとは、
①相続財産が細分化を不適当とするものであること(現物分割が不適当であること)
②共同相続人間に代償金支払いの方法によることにつき争いがないこと
③当該相続財産の評価額がおおむね共同相続人間で一致していること
④相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること
とされています。
①現物分割が不適当なケースとは、例えば、土地上に建物が建っていて底地を分筆して分けることができないなどそもそも現物分割が不可能な場合や、不可能ではないが現物分割によって財産の価値が著しく低下する場合,また、不動産などの遺産に対して一部の相続人が現にそこに居住している場合などが挙げられます。
また,④遺産取得者の支払能力も代償分割を決定する上では大きなポイントとなります。遺産分割審判では、この支払能力の有無が代償分割を決定するか否かを左右することになり、裁判所はこれを確認する必要があります。
代償金を支払えるかどうかは、預貯金や金融機関の融資証明書などで確認され判断されます。また、この代償金は,通常,一定の期間内に一括で支払うことが条件とされます。
(3)換価分割
遺された財産を売却するなどにより金銭へと換え、それを共同相続人間で分ける方法が、換価分割です。遺産を現状のまま受け取りたいと希望する相続人がいない場合に多く用いられる方法です。
例えば,相続人の誰とも縁遠い場所に実家があり,その実家を売却し金銭に換えた上で相続人間で分けるケースなどです。
*遺産分割審判においては
遺産分割審判では、換価分割は,現物分割や代償分割が共に難しい場合で採用されます。
実家売却の例で言えば、土地の上に建物が建っており現物分割は困難,かつ,実家の取得を希望する相続人はいるが、代償金の支払能力がないケースなどが考えられるでしょう。
遺産分割審判で換価分割の決定がなされる場合には、中間処分としての換価審判と終局審判の2通りがあります。
前者の場合は,競売もしくは任意売却によって財産が金銭化されます。(任意売却が可能となるのは共同相続人全てが賛成している時のみ)また、換価により生じた金銭は裁判所が定めた財産管理者が審判が終結するまで保管します。
終局審判によって遺産を換価する場合は,競売によって金銭化され、審判は終結しているのでそのまま相続人がそれぞれ金銭を受け取ることになります。
(4)共有分割
遺された財産の全部または一部を共同相続人が共有の状態で取得するのが共有分割です。
遺産分割では、本来共同相続人が共有する状態を解消することが基本的な目的となりますが、現物分割や代償分割、あるいは換価分割では問題の解決が困難だと判断された場合、やむなくこの共有分割が採用されることがあります。
共有分割されたのち、もしその共有状態を解消したいとなった場合は共有物分割を裁判所に請求(民法258条)するなどし、その解決を図っていきます。
6.預貯金の遺産分割(最高裁決定)

遺産分割の実務上大きな影響を与えることとなった最高裁平成28年12月19日決定(以下「本決定」といいます)についてご紹介したいと思います。本決定では、「預貯金は遺産分割の対象とならない」としてきた今までの判例を変更し、「預貯金は遺産分割の対象となる」とする初の判断を下しました。 以下、詳しく紹介していきたいと思います。
(1)今までの判例・実務の取扱い
まず本決定についてご紹介する前に、本決定により判例変更となった背景を知るために、今までの判例・実務における、遺産分割での預貯金の取扱いやその取扱いの問題点についてお話ししたいと思います。 具体例として次の事例を想定してみます。
【事例】
Aさんには、X、Y、Zという3人の子どもがいる。Aさんの妻はすでに亡くなっています。AさんはZを大変可愛がっていたので、3,000万円の土地を遺言で贈与することにして、6,000万円の預金については何も遺言を残さず亡くなった。
今までの判例で重要なものが2つあります。
①「相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」(最高裁昭和29年4月8日判決)
②「相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではない」(最高裁平成16年4月20日判決)
①②で言われている「可分債権」とは、性質上分割が可能で、分割給付を目的とする債権のことをいい、売買代金の請求権といった金銭債権がこれに含まれます。そして、判例・実務においては、その「相続財産中の可分債権」に預金債権も当然含まれているものとして取り扱われています。
こうした判例・実務により、預金債権は、遺産分割手続の対象とならず、相続分に応じて当然に分割されて、相続人が単独で有しているということになっていました。
上の【事例】についてみると、X・Y・Zがそれぞれ6,000万円の3分の1ずつである2,000万円ずつを銀行に返してくれという権利を持つことになります。そうすると、XとYは2000万円分の財産しか相続できません。それに対し、Zは、預金と、遺言で贈与された3000万円ぶんの土地を合わせて5000万円分の財産を取得できるという状況になり、Zが得をするということになっていました。
こうした相続人間の不公平を解消するため、実務上、当事者間(【事例】でいうX・Y・Z)で預金債権についても遺産分割の対象とするとの合意がある場合には、預金債権についても遺産分割の対象とできるとの例外がありました。しかし、相続人間で合意ができなかった場合(例えばZが一人反対した場合)には遺産分割の対象とはできないままでした。
なお、判例は金銭(最高裁平成4年4月10日判決)や定期郵便貯金債権(最高裁平22年10月8日判決)については、遺産分割の対象となると判断しており、預貯金だけなぜ取扱いが異なるのかという批判もあるところでした。
(2)最高裁による判例変更
本決定は、こうした相続人間で不公平な結果を招く状況を変えるために、上記②の判例を変更し、預貯金も遺産分割の対象になることを判断しました。
同決定は、理由として、
①遺産分割の仕組みは、共同相続人間の実質的公平を図るものであるから、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましい。また、実務上、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在する。
②預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められている。
③普通預金債権及び通常貯金債権は、いずれも、1個の債権として同一性を保持しながら、常にその残高が変動し得るものであり、預金者が死亡した場合にも、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはない。
④定期貯金は、事務の定型化、簡素化を図るという趣旨のもと、契約上その分割払戻しが制限されている。定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。
といったことを挙げ、①②に示された預貯金一般の性格等を踏まえつつ上記③④のような各種貯金債権の内容及び性質をみると、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
…以上説示するところに従い,最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。」と判断しました。
こうして、預金債権についても相続人の同意の有無にかかわらず遺産分割の対象となり、遺産分割の対象が広がることになるので、相続人間の公平な分割のために、選択肢が広がることは望ましいと言えます。
他方で、従前では、各相続人が法定相続分に応じて金融機関から払戻しを受ければ相続が終了した場合にも、今後は別途遺産分割手続が必要となってしまうという弊害もでてきます。
更に、銀行等の実務として、本決定により、預貯金は当然に分割されないとされたため、今後は遺産分割がない状態で払い戻しを行うことは困難になると考えられます。
(3)補足意見の問題意識
最高裁判所の判決文には、判決となった多数意見と別に、裁判官それぞれの個別意見が表示されることがあります。その内、「補足意見」とは多数意見に賛成であるが、意見を補足するものをいいます。
本決定では、複数の補足意見が付されており、例えば預金債権以外の可分債権(例えば貸金債権や不法行為に基づく損害賠償請求権など)についても遺産分割の対象にするべきでないかといったことや、相続預金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合にどういった手段をとればいいか、相続開始後に預金口座に入金されたお金についてどのように取り扱うかなどの問題意識や解決策の提案などがなされています。
個別意見はhttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdfをご覧ください。
(4)その他の判例について
その後、平成29年4月6日に出された最高裁判決では、信用金庫の普通預金、定期預金及び定期積金についても、「いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」と判断されました
全文→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/086670_hanrei.pdf
本決定、上記判決を合わせると、銀行・信用金庫の普通預金・外貨普通預金・定期預金・ゆうちょ銀行の通常貯金・定期貯金が遺産分割の対象になったことになり、現在一般に扱われている預貯金はほぼ遺産分割の対象になると考えてよいものと思われます。
また、投資信託受益権や個人向け国債について当然分割されず、遺産分割の対象となると判示した最高裁平成26年2月25日判決も合わせると、金融機関の扱う金融商品はおおむね遺産分割の対象となるものと考えてよいものと思われます。
(5)まとめ
このように本決定やその他の判例により、遺産分割の対象となる財産は広がり、現実の遺産分割の問題において、大変な影響を及ぼしております。
もし、今回取り上げた問題だけでなく、他にも相続や遺産分割についてお困りの方がいらっしゃいましたら、守口門真総合法律事務所へお気軽にご相談ください。
7.使途不明金問題について
(1)使途不明金問題とは

使途不明金問題とは,被相続人の生前又は死後,相続人の一部が被相続人の預金を無断で引き出したり,解約したりすることで生じる問題のことです。
被相続人の遺産分割手続を行っている最中,被相続人の生前又は死後に引き出された使途不明金が発覚することがよくあります。
使途不明金問題の対処方法については,家庭裁判所における遺産分割手続の中で解決できるものと,別途地方裁判所に訴訟提起を行わないといけないものに分かれます。
遺産分割手続の中で解決できるものとしては,使途不明金の引き出し時期,金額を特定できる場合で,かつ,①被相続人からの贈与(被相続人の同意あり)といえる場合か,②関与した相続人が使途不明金の自己使用・無断取得を認める場合が挙げられます。
①の場合,生前贈与(特別受益)の問題として取り上げることができ,②の場合,遺産の先取り(預かり現金)として,遺産分割手続に反映させることが可能です。
もっとも,それ以外の場合,①そもそも,使途不明金の引き出し時期,金額が特定できない場合や,②時期,金額の特定ができるものの,関与した相続人から合理的な使途の説明がない場合等には,遺産分割手続とは別途,民事訴訟を検討する必要があります。
(2)遺産分割手続と使途不明金
遺産分割手続は,家庭裁判所における調停・審判の手続で解決することができますが,そもそも,使途不明金の引き出し時期,金額が特定できない場合,家庭裁判所は,どれだけ使途不明金発生の疑いがある場合でも,原則,遺産探しには応じません。
遺産分割手続は,判明している確実な遺産のみに基づき進められることとなり,明らかとなっていない遺産については,別途地方裁判所への訴訟提起を促されます。
もっとも,当事者にとって,遺産分割手続とは別途,使途不明金に関する訴訟を行うことは著しい負担となりますので,使途不明金の引き出し時期・金額が特定できる場合,最初の数回程度は,遺産分割手続の中でも,使途不明金に関する話し合いをすることが可能なケースがあります。但し,その場合でも,数回の期日で使途不明金の問題を解決できない場合は,原則通り,別途訴訟提起を促される流れとなります。
最初の数回の期日で使途不明金の存在・金額が確定した場合,当該使途不明金については,関与した相続人の預かり現金として,遺産目録に計上する形になります。
使途不明金の存在・金額が確定せず,それ以外の遺産についてのみ遺産分割手続を行う場合は,新たに遺産が発見された場合の処理方法につき,条項に含める形になります。
(3)遺産分割調停で使途不明金問題が解決しない場合
この場合,使途不明金問題を遺産分割手続内で扱うことについて,当事者全員が同意していたとしても,使途不明金は遺産分割手続の対象とはなりません。
遺産分割手続の対象とするためには,当該遺産が,①相続時に存在し,②遺産分割時にも存在する必要がありますが,相続「前」の無断出金は①の要件を満たさず,相続「後」の無断出金は②の要件を満たさないからです。
詳しく説明しますと,相続「前」の無断出金については,預金に関し,そもそも相続時に存在しないため遺産ではなく,関与した相続人に対する返還請求権が遺産となりますが,返還請求権は相続時に法定相続分で分割されており,未分割の遺産ではないからです。
これに対し,相続「後」の無断出金については,①相続時に存在するため遺産となりますが,②分割時に存在しないため,遺産分割手続の対象とはなりません。
(4)使途不明金を遺産分割手続の対象としないことの不合理性
たとえば,被相続人をA,相続人をB,Cとして,Aの預金が1000万円存在し,別途AがBに対して1000万円の生前贈与をしているケースを考えます。
これをCの立場から見た場合,遺産分割手続の対象はAの預金1000万円であり,Bは既に生前贈与1000万円を遺産の前渡しとして受け取っているため,Cは本来,Aの預金1000万円を全て相続することになります。
しかし,このケースで,BがAの預金1000万円を無断解約していたという事実が存在し,それが遺産分割手続の対象とされない場合,相続時に預金1000万円は残っていないため,「相続時に存在する」という「遺産」の要件を満たさず,遺産分割手続の対象財産はありません。つまり,Cとしては,Bの生前贈与を問題視しようにも,それを清算する手立てがなくなってしまいます。
CはBに対し,使途不明金として,Bが無断解約した1000万円のうち,自身の法定相続分に相当する500万円の請求をすることはできますが,原則として,それ以上にBに対して請求することはできず,取得分は500万円に留まります。
このような結論は明らかに不合理です。しかし,使途不明金の問題は,原則,民事訴訟の場で証拠を突き合わせてその有無を判断すべき事柄ですから,当事者が同意しない場合に,結果的に白黒付けることができない家庭裁判所が,他方当事者の要望のままにその問題を議論すれば,いたずらに手続を長期化させることになりかねません。
したがって,家庭裁判所が,数回の期日を限度として話し合いの場を設け,それ以降は分割の対象から除外しようとするのは,やむを得ない運用であると考えられています。
(5)小括
以上のとおり,使途不明金の問題は,非常に難しい問題をはらんでいます。
守口門真総合法律事務所では,相続分野の案件を数多く取り扱っております。
相続についてお悩みの方は,いつでもお気軽にご相談ください。
8.遺産共有状態での共有物分割手続の見直し(令和5年民法改正)
(1)民法改正による共有物分割手続の見直し

令和5年4月1日,改正民法が施行され,相続によって遺産共有状態が生じた場合の共有物分割手続が見直されました。
前提として,相続が発生するとその瞬間,亡くなった方の不動産は,相続人全員の遺産共有状態となります。
登記簿上は亡くなった方の名義のままであっても,亡くなった方は不動産の所有者にはなり得ませんので,実際は,相続人全員の共有状態として扱われます。
(2)旧民法の問題点
これまでの旧民法では,相続によってこういった遺産共有状態が発生した場合,共有物分割を求める相続人は,いきなり共有物分割手続を行うのではなく,まずは遺産分割協議によって各自の相続分を定め,その後,共有物分割手続を行うべきとされてきました。
このため,相続人が共有物分割を求める場合,まずは遺産分割協議を行い,その後に共有物分割手続を行う必要があったため,相続人は二重の手続を強いられていました。
(3)改正民法の変更点
今回の民法改正によって,相続開始から10年間が経過すると,相続人からの異議の申出がない限り,遺産分割協議を行うことなく,共有物分割訴訟のみによって,共有物の分割請求が可能になりました(民法258条の2)。
これは,同じく今回の民法改正によって,長期間経過後の遺産分割が見直され,相続開始時から10年間経過後は,原則として法定相続分や指定相続分による分割しかできなくなったこと(民法904条の3)と大きく関連しています。
今回の民法改正によって,相続発生から10年以内に遺産分割協議を行うことが望ましい,という法の立場が明確にされ,この期間を越えて以降は,遺産分割協議の機会を相続人に保障することよりも,相続手続きを円滑に進めることを重視するという立場が明らかにされました。
今回の法改正は,言い方を変えれば,遺産分割協議の期間として10年間を保障するので,その期間内に協議ができなければそれは自己責任であり,その後は具体的相続分を争わせないことで,スムーズに相続手続を進めるという方向に舵を切る,ということです。
(4)小括
このような法改正の背景には,遺産分割協議が行われないまま遺産が放置されることに対する強い危機感が窺われます。
冒頭説明しましたとおり,相続が発生した瞬間,亡くなった方は遺産の所持者ではなくなり,相続人が遺産の所持者となります。
今回の法改正は,早期の遺産分割協議の促す強いメッセージと言えますので,相続が発生した場合は安易に放置することなく,お早めに専門家までご相談ください。
※相続土地国庫帰属制度
相続人が、相続した土地を放置し、将来「所有者不明土地」となることを予防するために、令和5年4月27日から、相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
(1)国に帰属することができない土地
もっとも、以下のような土地は、土地の管理・処分をするに当たって過分の費用又は労力を要する土地として国庫帰属の承認申請がそもそも認められなかったり、国庫帰属不承認となったりします。
ア 申請することができない土地(相続土地国庫帰属法2条3項各号)
・建物の存在する土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定される土地
・土壌汚染がある土地
・所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
イ 帰属の承認がされない土地(相続土地国庫帰属法5条1項)
・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
・通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
(2)国庫帰属の申請権者
国庫帰属申請ができるのは、相続や遺贈によって、土地の所有権を取得した相続人です。また、土地が共有地である場合は、共有者全員で国庫帰属の申請をしなければなりません。
加えて国庫帰属申請は手続きの代理が認められておらず、申請手続きは申請者本人が行う必要があります。
(3)手数料等
ア
相続土地の国庫帰属の申請時には、申請した土地の国庫への帰属が認められるかの審査があり、その審査手数料として土地1筆につき1万4000円の審査手数料が必要となります。
また、申請書には、承認申請をする土地の位置及び範囲を明らかにする図面や、隣接する土地との境界点を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真等の添付が必要となります。
イ
そして、審査を経て、申請をした土地の国庫への帰属が無事に承認された場合、土地の10年分の管理費用相当額を負担金として国に納めなければなりません。
負担金の最低金額は20万円ですが、土地の存在する地域や土地の種類によっては、土地の面積に応じて負担金が加算されます。
(4)小括
以上のように、令和5年4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」が開始されましたが、当該制度は、相続した土地を放置し、将来「所有者不明土地」となることを予防するという目的である一方で、国の予算と労力を使って国庫帰属地を管理することになることから、土地の管理・処分に過分の費用を要する土地は国庫帰属することが認められず、また、国庫帰属が認められるとしてもそれなりの費用が掛かる制度設計となっています。
そのため、誰もが相続し管理・処分をすることを躊躇するような土地については、依然として問題の解消は困難な状態ですが、不要地の処分方法の選択肢が増えたとういう点は歓迎すべきことです。
相続が発生した場合は、相続土地国庫帰属制度も含め様々な選択肢があり、また、様々な法律問題が生じますので、お早めに専門家までご相談下さい。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](../common/img/header_tel.png)
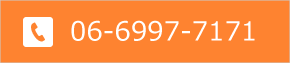






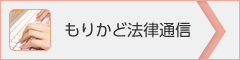

![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)

![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](../common/img/btn_sp_tel.png)


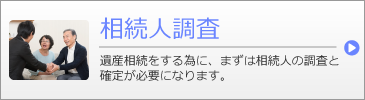


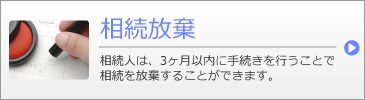
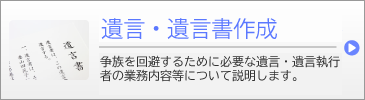
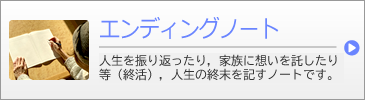

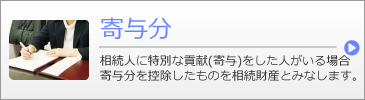
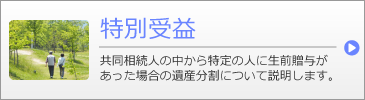
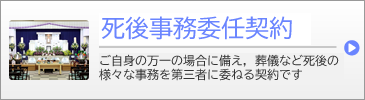
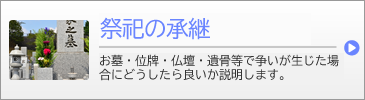
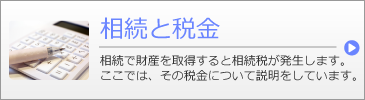
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](../common/img/bnr_contact01.png)

