遺産分割調停が不成立になると「遺産分割審判」になる?
遺産分割における話し合いの流れ
1、遺産分割協議

遺産分割を行う場合、まずは相続人同士で話し合いをすることになります。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議をすることでスムーズに合意できればいいのですが、現実的には感情論で話がこじれたり、話し合いに参加したがらない相続人が出たりすることも多いようです。
遺産分割協議の成立は相続人全員の合意が前提になるため、相続人の誰かが内容に不服を感じて不同意になった場合、不成立になります。
不成立になる時は「相続人同士で話し合ったけれど、これ以上は話をしても全員が合意することはないだろう」という状況になっていることが想定されます。
不動産の相続方法や寄与分・特別受益などで揉めてしまうと、不成立になる可能性は高いでしょう。
また「何度も調停を実施しているのに、全く参加してくれない相続人がいる」という場合も、不成立になることが考えられます。
全員の合意が得られない場合、遺産分割協議は不成立となることを覚えておきましょう。
2、遺産分割調停の申立て
遺産分割協議では話がまとまらない場合、次の段階として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。
話し合いへの参加を拒んでいた相続人には、家庭裁判所から呼び出し状を送付してもらうことも可能です。
遺産分割調停では、家事審判官1人と調停委員2人が各相続人の意見や希望する分割方法を丁寧に聞いたうえで、第三者的な観点からもっとも平等とされる解決案や落としどころを提示してくれます。
ただし、この提示された調停案に従う必要はなく、相続人同士が歩み寄りできなければ調停は不成立になります。
3、遺産審判手続
遺産分割調停でも不成立になった場合には、家庭裁判所で遺産審判手続をすることになります。
調停不成立の際には自動的に審判手続に移行するため、改めて申立てをする必要はありません。
審判手続では、今までのように相続人同士の話し合いによる合意を目指すのではなく、一般的な民事訴訟のように各当事者が自分の主張と根拠になる証拠を提出し、それに基づいて裁判官が客観的にどちらの言い分に正当性があるか判断をしていくことになります。
こうした過程を経て審判された家庭裁判所の決定には強制力が認められるため、分割方法や割合に納得できない相続人がいたとしても家庭裁判所の決定に従わなければいけません。
ただし、当該審判の決定に不服がある相続人は2週間以内であれば即時抗告をすることができ、高等裁判所で再度審理してもらう権利は認められています。
このように遺産分割は協議→調停→審判の流れで進行し、統計的には調停と審判で6回から10回の期日に参加する必要があり、1年~2年以内に結論が出ることが多くなっています。
遺産分割調停と遺産分割審判は何が違う?
「遺産分割調停」が不成立になった場合に「遺産分割審判」へと進む点は、前述したとおりですが、何が違うのかもう少し詳しくご説明します。
遺産分割調停は話し合うことが基本です。
調停委員2名が間に入って、話を進めていきます。
調停委員が話を聞いてくれるため、主張を訴えやすく、立証資料は必須ではありません。
一方で、遺産分割審判は、審判官が遺産分割方法を指定します。
調停委員が間に入ることはありませんし、当事者が参加していなくても遺産分割方法を決められるので、相続人の誰かが参加を拒否し出席しなくても進められます。
審判の場合、たとえ当事者が「納得できない」と言っても、審判官が法律に則って遺産分割方法を決定しますし、結果には強制力があります。
審判員が、遺産となる家の競売命令を出した場合、反対する相続人がいても競売となってしまう可能性があるので、しっかりと準備し対応することが大切です。
主張したいことがあれば、資料などの提出が必要ですので、弁護士などの専門家を頼ることも検討しましょう。
遺産分割審判の注意点
遺産分割で揉めやすいのが不動産の分割方法です。
相続人同士の話し合いで解決する場合には、相続人の1人が単独相続して他の相続人に代償金を支払う方法(代償分割)がベターな選択肢のひとつとされています。
しかし遺産分割審判の場合には、もっとも客観的公平性が担保されることを根拠として、競売によって売却した代金を分配する方法(換価分割)が選ばれることが多いのです(家事事件手続法194条)。
通常、不動産売却の場合には時間をかけて見積もりを比べたり価格の検討をしたりしますが、競売の場合には相場よりも安い売却金額で落札されてしまう可能性が大きいことが問題点になります。
すなわち、不動産の分割で揉めた場合に審判手続での決定を待つことは、相場よりも安い売却代金にしかならず、相続人全員が損をしてしまうのです。
不動産の遺産分割の場合には、特別な事情がない限り、審判手続に移行する前の調停段階で歩み寄ったほうがお互いのためになると言えそうです。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
相続の関連コンテンツ
- 遺産分割調停が不成立になると「遺産分割審判」になる?
- 事実婚のパートナー(内縁の夫・妻)がもしもの時に相続はどうなる?
- 障害児の親が面倒を見る家族・兄弟に全財産を相続することは可能?
- 自分以外の兄弟が親の生前にまとまった額を受け取っていた場合の相続は?
- 実家を生前贈与する場合の問題点と名義変更の方法について
- 孫への贈与が特別受益の対象になるケースや相続における注意点とは?
- 生涯独身で一人暮らしの高齢者の相続はどうなる?親族が面倒を見た場合は?
- 銀行の「遺言信託」を利用するメリットとデメリット
- 特定の子どもを相続人から除外(相続排除)することは可能?
- 子どもに喜ばれる生前贈与のやり方や節税のための注意点とは?
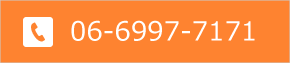


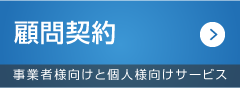
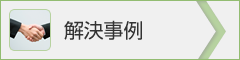
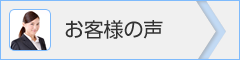
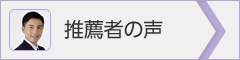
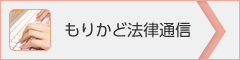
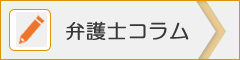
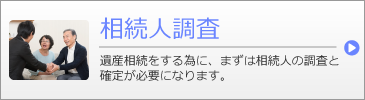
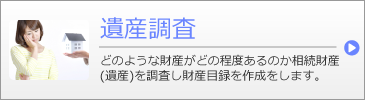
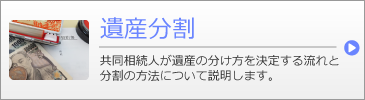
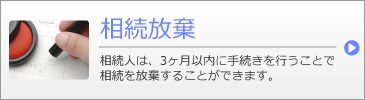
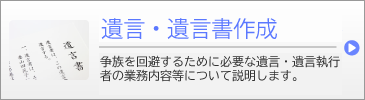
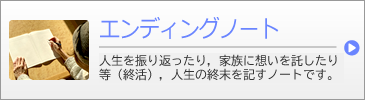
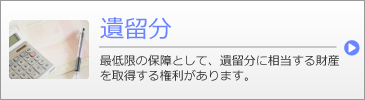
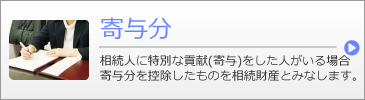
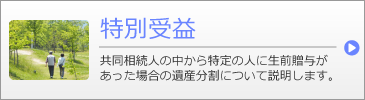
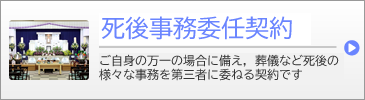
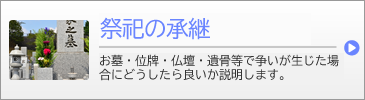
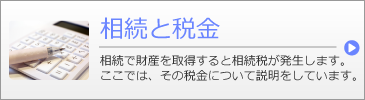
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)
![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](/common/img/btn_sp_tel.png)

