遺留分に関するトラブルと解決策 – 弁護士によるサポート
遺留分とは、法定相続人に最低限保証される相続財産の割合を指します。
遺言によってすべての財産が特定の相続人や第三者に渡る場合でも、遺留分を持つ相続人は、その取り分を請求する権利があります。
しかし、遺留分を巡るトラブルは、相続人間での対立を引き起こし、感情的な争いに発展することが少なくありません。
当法律事務所では、遺留分に関する権利の主張や請求に対して法的なサポートを提供し、依頼者が納得のいく解決を得られるようお手伝いします。
当法律事務所のサポート内容
遺留分侵害額請求のサポート
遺言書の内容や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことで取り戻すことができます。
当法律事務所では、請求の手続きを迅速かつ確実にサポートします。
遺留分侵害額請求への対応
他の相続人や第三者から遺留分侵害額請求を受けた場合、依頼者の立場を守るための交渉や法的手続きを行います。
遺言書の内容確認とリスクの評価
遺言書が遺留分を侵害している可能性がある場合、その内容を法的に評価し、リスクを最小限に抑えるためのアドバイスを提供します。
相続人間の調整とトラブル防止
遺留分を巡るトラブルが家族間の対立を深めないよう、公平な立場から調整を行い、円満な解決を目指します。
時効の確認と対応
遺留分侵害額請求には原則として1年の時効があります。当法律事務所では、請求可能期間内に手続きを進めるためのサポートを行います。
生前対策のアドバイス
遺留分を巡るトラブルを未然に防ぐため、生前贈与や遺言書の作成段階での対策を提案します。依頼者の意向を尊重しつつ、法的リスクを抑えるための支援を行います。
調停・訴訟の代理
遺留分を巡る争いが調停や訴訟に発展した場合でも、依頼者を代理して解決に向けた交渉や法的対応を行います。
遺留分におけるトラブルを未然に防ぐために
遺留分を巡るトラブルは、事前に対策を講じることで大きく軽減することができます。
当法律事務所では、遺言書の内容や生前贈与の計画段階から法的アドバイスを提供し、相続人間の争いを防ぐためのサポートを行っています。
また、遺留分侵害額請求が発生した場合でも、迅速かつ丁寧な対応で依頼者の権利を守ります。
遺留分に関する疑問や不安がございましたら、ぜひ当法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、依頼者の立場に寄り添いながら、納得のいく解決に向けたお手伝いをいたします。
遺留分

我が国の相続制度では、原則として被相続人(お亡くなりになった方)が遺言によって自由に財産を処分することができます。
例えば、遺言によって家族の中の一人だけに財産を渡すこと、あるいは渡さないこともできますし、また、家族以外の他人に全財産を譲ることもできます。
しかし、そのように偏った財産処分をする場合、往々にして不遇を受けた相続人が生活に窮することになりかねません。
そのため、一定の相続人には、最低限度の保障として、相続財産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利が認められています。
それが遺留分制度というものです。
民法に定められた遺留分権利者および遺留分の割合は、以下のとおりです。
配偶者・直系卑属のどちらか片方だけの場合 法定相続分の1/2
配偶者・直系卑属の両方の場合 法定相続分の1/2
直系尊属だけの場合 法定相続分の1/3
兄弟姉妹だけの場合 遺留分はありません
※複数の遺留分権利者がいる場合、法定相続分で割って計算することになります。
※また、上記のように兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分は保障されていないことに注意が必要です。
遺留分減殺請求
ただし、遺留分は、相続開始と同時に当然に上記割合の財産が得られるわけではなく、遺留分権利者が請求をしなければなりません。
この請求のことを遺留分減殺請求と呼びます。
遺留分減殺請求を行う場合、相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時から、1年以内に請求しなければなりません。
また、たとえ遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始の時から10年経過することで請求する権利は消滅します。
このように期間の制限があることにも留意する必要があります。
遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求権は、遺言または贈与により相続財産とみられる財産を得た者に対して、その侵害額を請求する意思表示をすることにより行使します。
一般的には、後日の紛争も見越して、まず内容証明郵便などにより請求をかけることになります。
相手が任意に請求に応じてくれるとはかぎりません。
その場合、調停・訴訟といった法的手段を検討することになります。
しかし、相手が遺留分権利者なのか、遺留分権利者であれば遺留分が侵害されているのか、侵害されていた場合は具体的にどのように回復するかなどは、なかなか当事者で判断することは難しいと思います。
守口門真総合法律事務所では、遺産の問題について初回無料相談を承っておりますので、なるべく早く御相談に来ていただければと思います。
遺留分制度に関する民法改正について

2018年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し(公布は同年7月13日),一部の規定を除き,2019年7月1日から既に施行されています。
ここでは,その中でも遺留分制度に関する改正について御説明致します。
1.従来の遺留分制度の問題点
(1)改正前の遺留分減殺請求権の性質
遺留分制度は,前記「遺留分」という点で説明しましたとおり,一定の相続人に、最低限度の保障として、相続財産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利を認めたものです。
遺留分減殺請求権は,一方的な意思表示により法律効果が発生する形成権ですので,減殺請求の意思表示をすれば、相続財産に対し、遺留分割合の共有持分を持つことになっていました(これを「物権的効力」といいます)。
つまり,遺留分減殺請求権を行使することにより、相続財産を構成する各財産について、法律上当然に遺留分割合の共有持分を取得するということです。
あくまで,遺留分減殺請求権は,現物で返還を求められる権利を得ることを原則とする一方、贈与を受けた側が、物ではなく金銭で支払うこと(価額弁償)を選択した場合にのみ、金銭を請求できることとしていたため,贈与を受けた側が価額弁償を選択しない場合には,権利関係が複雑になるという問題点が指摘されていました。
(2)具体例
例えば、相続人が子A・Bの2名で,「Aにすべての財産を相続させる」との遺言があり,相続財産に土地があった場合を想定します(この場合,Aを「受遺者」といいます)。
このケースにおいて、BがAに対し遺留分減殺請求権を行使したという場合、Bは,法律上当然に、土地について1/4の共有持分を取得します。
このように共有状態が生じた場合,例えば土地を売却するときには、他の共有名義人の同意が必要になり,また共有名義人が亡くなれば、その持分は相続の対象となるため,元々A・B2人の共有名義だったのが、3人、4人と増えていく可能性があったりするため,処分が困難になります。
そして,この共有状態を解消するためには、共有物分割請求を行い、共有者間で話し合いがつかなければ、訴訟等で解決を図らざるを得ないことになります。
2.遺留分制度の改正点
(1)改正のポイント
上記問題点を解決するため,改正民法では,物自体の返還の権利を原則としていた遺留分侵害額請求権を、金銭での返還を求める権利と性質を変えました。これに伴い,遺留分減殺請求権という名称も「遺留分侵害額請求」と変わりました(改正民法1046条1項,1048条)。
つまり,上記例で,不動産の評価額が1000万円であった場合,BはAに対して1000万円×1/4=250万円を請求できるのみとなりました。
このような改正により,前記で指摘しました権利関係が複雑になるという問題点が解消されることとなります。
(2)遺留分侵害額請求を受けた受遺者の期限の許与
上記改正により,受遺者(上記具体例のA)としては,遺産が不動産しかない場合でも金銭を請求されることになりました。そうすると、不動産を売却するまでの間や、金策をとる間が必要となります。
そこで,遺留分侵害額請求を受けた受遺者等が金銭を準備できない場合に備え,改正民法1047条5項では,受遺者等が,裁判所に対して,遺留分侵害額債務の全部又は一部の支払について、相当の期限を許与してもらうことができると定めています。
つまり,受遺者等が裁判所に対し,申立てをすることで、遺留分侵害額の支払について、支払期限を設けてもらうということです。
3.小括
上記のように,遺留分制度に関する改正の主要な点をご説明いたしました。その他にも遺留分制度について,その算定方法等も改正点があり,遺留分権利者であれば遺留分が侵害されているのか、侵害されていた場合は具体的にどのように回復するかなどは、なかなか当事者で判断することは難しいと思います。
守口門真総合法律事務所では、遺産の問題について初回無料相談を承っておりますので、なるべく早く御相談に来ていただければと思います。
遺留分制度における相続法改正の影響
1. 昨年施行された相続法の一部改正

2018年7月6日,相続法を一部改正する内容の法律が成立し(公布は同年7月13日),一部の規定を除き,2019年7月1日から施行されています。
遺留分制度に関する相続法改正のうち,①遺留分減殺請求権から生ずる権利の金銭債権化,②裁判所による相当の期限の許与につきましては,以前の記事で説明させて頂きましたので,下記URLをご参照ください。
今回は,遺留分制度に関する相続法改正のうち,以前の記事で説明できなかった箇所について,説明させて頂きます。
※ご参照
相続法改正について その2 ~遺言制度・遺留分制度~
https://murakami-law.org/1065/
2. 相続人に対する贈与に関する扱いの変更
(1)旧法の場合
遺留分侵害額を算定する場合,まず,基礎となる財産額の全体を明らかにする必要がありますが,基礎となる財産額は,①相続開始時財産額+②贈与財産額-③債務総額によって定まります。
旧法においては,②贈与財産額は,以下のⅰ~ⅳによって構成されていました。
ⅰ 相続開始前1年間の贈与
ⅱ 相続開始1年前よりも以前に,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与
ⅲ 不相当な対価で行った有償行為のうち,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われたもの
ⅳ 相続人に対する婚姻もしくは養子縁組のため,または生計の資本としての贈与(特別受益に該当するもの)
※相続開始よりも相当以前にされたものであっても,特段の事情のない限り,すべて贈与財産額に含まれるものとされていました。
(2)新法の場合
これに対し,新法では,②贈与財産額に関し,相続人に対する贈与に関する扱いが大きく変更されました。具体的には,相続人に対する贈与については,贈与した財産の価額に含まれるのは,ⅳの特別受益に該当する贈与に限られ,その期間も相続開始前の10年間に限定されました(新法1044条3項)。
すなわち,旧法の場合のⅰ,ⅱについては,相続人以外の者に対する贈与のみ適用され,相続人に対する贈与については,ⅳの特別受益に該当する贈与のうち,相続開始前の10年間に行われた贈与及び相続開始10年前以前に,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与のみが,贈与財産額を構成することになりました。
3. 遺留分の負担割合に関する大きな変更はなし
遺留分侵害額を誰がいくらずつ負担するのか,という遺留分の負担割合については,相続法改正によって,特段大きな変更はありません。
以下,遺留分の負担割合について,簡単に確認します。
(1)受遺者と受贈者がいる場合
ア 新法1047条1項1号は,「受遺者と受贈者があるときは,受遺者が先に負担する」と規定しており,旧法における減殺を受けるべき順位と変わりはありません。
もっとも,「相続させる」とする遺言により,特定の財産が承継された場合,遺言による相続分の指定により遺留分が侵害された場合は,遺贈と同順位に扱われます。
イ 具体例
たとえば,父Aの相続人が,母B,本人C,妹Dのケースで,AがBに4000万円生前贈与を行い,「甲土地(3000万円)をDに相続させる。預貯金3000万円はDの子Eに遺贈する。」との遺言書を作成していた場合,何も受け取れなかったCは,財産額1億円(4000万+3000万+3000万)×法定相続分4分の1×遺留分割合2分の1=1250万円の遺留分侵害額請求権を有することになります。
この遺留分侵害額の負担割合を定める場合,遺留分額を控除して算出するとの裁判例に従うと,Dについては,3000万円からDの遺留分額1250万円を控除した1750万円を,Eについては遺留分が存在しないので,3000万円全額を基礎に負担割合を定めます。したがって,DとEは,Cの遺留分侵害額1250万円について,1750:3000の割合で遺留分を負担することになります。
(2)複数人に同時に贈与した場合
新法1047条1項2号は,受遺者が複数ある場合と同様,受贈者が複数あるときにおいても,同時に贈与された場合には,価格割合に応じて遺留分侵害額を負担することを定めています。なお,この場合も,遺留分の負担割合を算出する際には,遺留分額を控除した金額で比較することとなります。
(3)複数人に異時贈与した場合
新法においても,旧法と同様,後の贈与における受贈者から順次,前の贈与における受贈者が,遺留分侵害額を負担することになっています。
4. 小括
改正相続法は,一部規定を除き,2019年7月1日から施行されております。
当事務所は,地域密着型法律事務所として相続分野に力を入れております。
遺留分侵害額を請求するにあたっては,誰にいくらずつ請求できるのかという計算方法が非常に複雑です。遺留分侵害額の請求も含め,遺言相続についてのご相談は,守口門真総合法律事務所にぜひご相談ください。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](../common/img/header_tel.png)
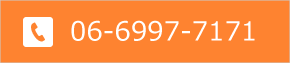






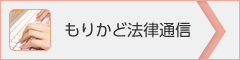

![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](/common/img/bnr_contact01.png)

![ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)](../common/img/btn_sp_tel.png)


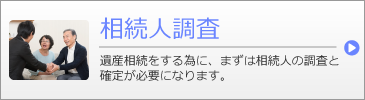


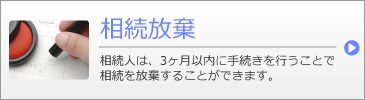
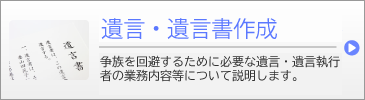
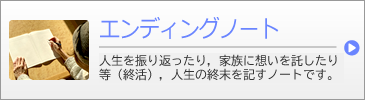

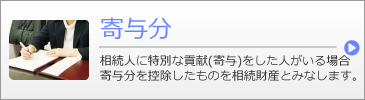
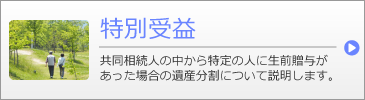
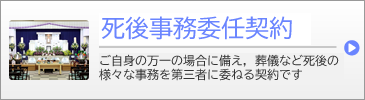
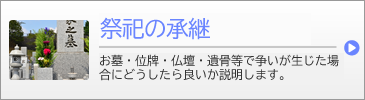
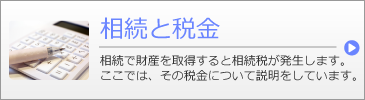
![HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません](../common/img/bnr_contact01.png)

