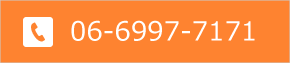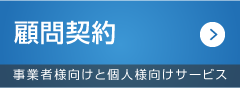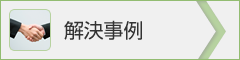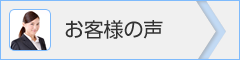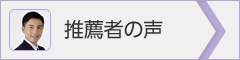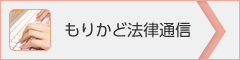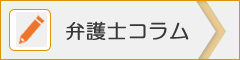1 リバースモーゲージが注目されている背景 高齢化社会といわれて久しい現代,日本の人口の4人に1人が高齢者という状況です。高齢者が保有する金融資産や不動産は他の年代と比べて多いのですが,高齢者世帯の家計収支状況を見ると, […]
続きを読む »弁護士コラム
保証会社に解除権を付与する条項の適法性
賃貸借契約と,これに伴う保証契約とは,本来,別個の契約となります。しかし,ほとんどの場合,同時に締結されており,相互に密接な関係を有している契約といえます。 今回は,家賃債務保証会社による賃貸借契約の解除権を認める契約条 […]
続きを読む »保証契約に関しての民法改正
1 保証契約とは 「保証契約」とは,保証人が,債権者との間で,借金の返済や代金の支払などの債務を負う「主債務者」がその債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約をいいます。 主債務 […]
続きを読む »交通事故(物損事故)で取引上の評価損が問題となった解決事例
1 事案の概要 被害者が自動車を駐車場に駐車していたところ,被害者が不在の間に,加害車両が被害車両に衝突しており,被害車両が破損した物損事故案件です。 本件事故により,被害車両の左後方部からタイヤハウス,バンパーにかけ […]
続きを読む »賃貸借契約に関しての民法改正
平成32年4月1日より,改正民法の施行が予定されており,賃貸借契約に関しても影響が出てきます。不動産賃貸借契約など,皆様の居住や事業の基盤になる契約についても,契約書を見直す必要があります。不動産業者だけでなく,地主,家 […]
続きを読む »![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](/common/img/header_tel.png)