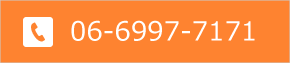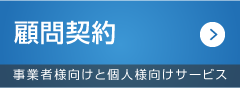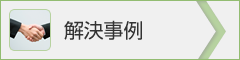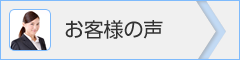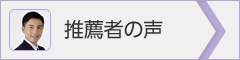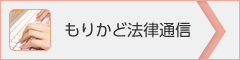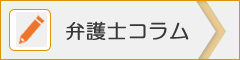守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。 「遺贈する」と「相続させる」との違いにつき,御相談を受けることがありますので,本日は,この点につき解説を致します。 「遺贈する」と「相続させる」をしっかり使い分けましょう […]
続きを読む »新着情報・トピックス
兄弟姉妹が親の生前に遺産相続の放棄を希望した場合の対応
守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。兄弟姉妹が「もし親が亡くなったら財産はいらない」と言っている場合の対応について、よくご相談を受けますので、本日はこの点の説明をさせていただきます。 兄弟姉妹の中には「親からの支 […]
続きを読む »民法改正 ~保証に関する規定の見直し~
1 保証に関する規定の見直し 平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。 皆様の生活に影響する部分として,民法改 […]
続きを読む »父親が亡くなった時に遺産相続で気を付けたいこと
守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。片親が亡くなった場合の相続につき、よく御相談を受けますので、本日はこの点の解説をさせていただきます。 両親のうち父親が先に亡くなった場合、母親と子どもが法定相続人です。ただし、 […]
続きを読む »借地上の建物の名義変更について
1 はじめに 土地を借りて,その上に自宅等の建物を持っている場合,地主との関係で様々な法律問題が発生します。ここでは,特に借地上の建物の名義変更をする場合について,御説明したいと思います。 2 借地上の建物を贈与・売却 […]
続きを読む »![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](/common/img/header_tel.png)