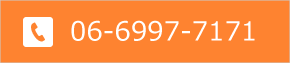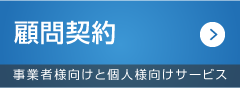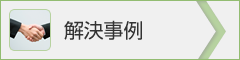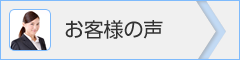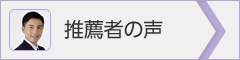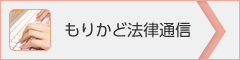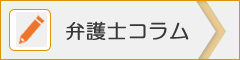1 「人手不足」関連倒産 2020年1月,東京商工リサーチは,2019年の企業の倒産状況につき,「人手不足」関連倒産は426件(前年比10.0%増)で,調査開始以来最多を記録したことを発表しました(http://www. […]
続きを読む »新着情報・トピックス
解決事例(遺留分減殺請求)
1.事案の概要 相談者は,弊所へ相談に来られる9か月前にお父様が亡くなられましたが,お父様が生前に公正証書遺言を作成していたという事案でした。法定相続人は,相談者以外にお母様と弟の2名,つまり合計3名で,法定相続割合は, […]
続きを読む »自己破産に関する反省文・生活再建策の作成について
1 反省文・生活再建策の作成とは 自己破産を行う場合の同時廃止手続とは,債権者に対して配当すべき財産がないことが明らかな場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止を決定する手続を言いますが(詳しくは,「破産管財事件と […]
続きを読む »成年被後見人の遺言作成(民法973条)の事例
1 相談内容 相談内容は,相談者のお父様が過去に交通事故に遭い,頭部外傷を受けて一時寝たきり状態となっていたが,現在では回復し,将来の相続に備えて遺言を作成したいというものでした。 当初の相談の主旨は,お父様が交通事故に […]
続きを読む »労働者からの未払賃金請求に経営者(依頼者)の主張に沿った勝訴的和解を実現した事例
2019年12月30日|解決事例
1.事案の概要 依頼者は,経営者の方で,相手方より未払賃金請求をされている方でした。 依頼者は,相手方との間で,業務請負契約を締結した認識でしたが、相手方は、自身は労働者であるということを主張し,未払賃金請求をしている状 […]
続きを読む »![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](/common/img/header_tel.png)