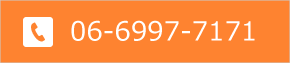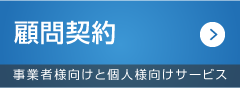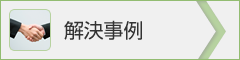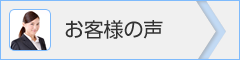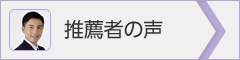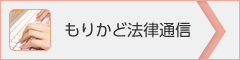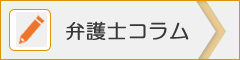1 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 令和2年6月12日,「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。この法律は,①サブリース契約の適正化,②賃貸住宅管理業の登録制度化を目的としています。賃貸管理 […]
続きを読む »新着情報・トピックス
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報
2020年04月28日|企業法務, 借金問題, 弁護士コラム
新型コロナウイルスの感染者数は,増加の一途を辿り,現段階で感染拡大が終息する見通しがない状況にあります。このような状況において,中小企業の皆様が直面する法律問題に対応する必要が生じております。 もっとも,新型コロナウイル […]
続きを読む »所有者不明土地問題―土地の相続への影響について
1 所有者不明土地問題 2019年12月3日,法制審議会民法・不動産登記部会において,所有者不明土地問題等に関する民法等の改正に関する「中間試案」が取りまとめられました。 所有者不明土地とは,不動産登記簿により所有者が直 […]
続きを読む »会社の通常清算の解決事例
枚方市に事務所を置く,とある株式会社から、通常清算の御依頼を受けて,守口門真総合法律事務所において,遂行させていただいた事例を御紹介します。 御依頼のきっかけは,代表取締役が死亡したが,会社の後継者がいないためでした。 […]
続きを読む »自己破産のご相談の解決事例
1.事案の概要 相談者は,門真市の方で,債務整理で相談を受けました。相談者は貸金業者1社より約120万円の借入れがありました。 2.方針の検討 相談者の借入金額は約120万円と,比較的少額で,相談者の意向としては返済をし […]
続きを読む »![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](/common/img/header_tel.png)