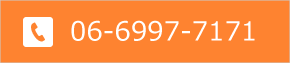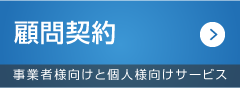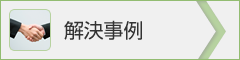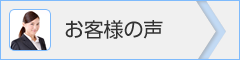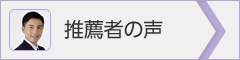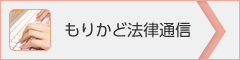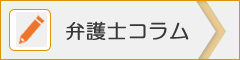1 事案の概要
15年ほど前に離婚された女性からのご依頼でした。
これまで支払われていた子どもの養育費が突然、支払われなくなったため、ご相談に来られました。
まず、守口門真総合法律事務所の弁護士において、通知文書を送付し、養育費の支払いを再開することと未払いの養育費の支払いを求めましたが、相手方からは応答がなく、家庭裁判所へ調停を申し立てることとしました。
2 調停における法的な問題点
養育費は、離婚の際に、「子の監護に要する費用」(民法766条1項)と
して、その分担を定めることとされています。これは、扶養義務のうち、親子間における扶養義務である「生活保持義務」、すなわち、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務」と解釈されています。具体的な養育費の額については、裁判実務上、子どもの数と年齢などの家族構成と両親の収入状況とで算定されます。これを一般化した養育費算定表と呼ばれるものが用いられています。
しかしながら、今回の事案では、一般化できない事情があり、この養育費算定表を用いることが出来ませんでした。その事情というのは、元妻が再婚した相手がおり、再婚相手と子どもとが養子縁組をしていたことです。
法的には、養子縁組をした場合、第一次的な監護義務・扶養義務は養親にあります(民法818条2項、820条)。もっとも、この場合でも、実親は二次的に監護義務・扶養義務を負うとされますが、この、「二次的な監護扶養義務」が具体的に何を指すのかについて、裁判例の蓄積はない状況でした。そのため、調停において、相手方である元夫から、養子縁組をしたことを理由として、監護義務・扶養義務は二次的なものとなっており、具体的な養育費の支払い義務はないとの主張がなされました。
3 紛争の解決
当事務所の弁護士の調査の結果、裁判例の蓄積はないものの、監護義務・扶養義務が、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務」であることからすれば、二次的であれ、実親も監護義務・扶養義務を負うのであって、再婚相手である養親が低収入である場合や仮に実親が一時的に扶養義務を負う場合の養育費との差額がある場合などには、個別具体的な事情のもと、実親が養育費を負担することもあると考えました。
今回の事案では、実親である相手方が調停に自分の収入を示す資料を出さないとか、本来別問題である子どもとの面会交流を引き換え条件に求めるとか、具体的な養育費の算定について多々問題がありました。しかし、子どもの年齢、養育費の支払い履行、子どもとの面会交流など様々な事情を考慮して、当方弁護士が調停委員を交えて相手方を納得させるよう説得した結果、月額2万5千円の養育費の支払いを認める調停が成立しました。
![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](/common/img/header_tel.png)